2017年3月10日
人権擁護協力会「人権のひろば」
「どう話すか」は、とても大事です
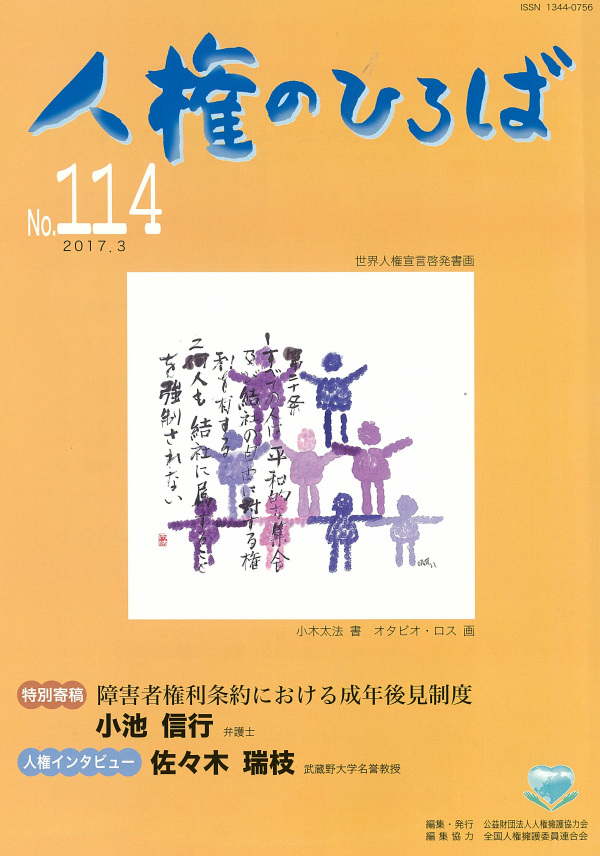
| 「どう話すか」は、とても大事です 佐々木 瑞枝 武蔵野大学名誉教授 |
聞き手 東京都連 甲野 恵美 |
|
-先生は、長年、外国人に日本語を教えてこられ、現在は日本語教師の養成に携わるとともに、日本語の中にあるジェンダーについての研究をライフワークにされていると伺いました。 今日は、日本語の面白さや難しさ、ジェンダーなどについてお話をお聞きしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 実は、親御さんから、帰国子女であるお子さんが「鉛筆を数えるとき、なぜ〝一ぽん”〝二ほん″ 〝三ぼん″と変わるの?」と質問してきて返答に窮したという話を聞きました。改めて考えてみますと、私も「そう言うから」としか答えられないと気づきました。 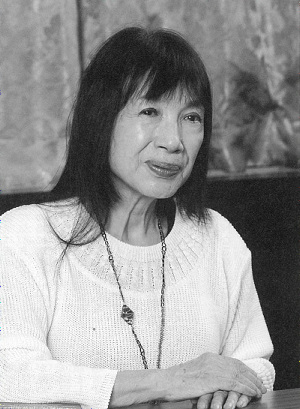 面白い質問ですね。 〝本〟 や〝個〟は助数詞と言いまして、数を表す言葉の後ろに付けて数量を表します。 ”個”は”一こ”、”二こ”、”三こ”…と変化しませんが、”本”を例にとって言い方をアルファベットにしますと、一ぽんP、二ほんH、三ぼんB、四ほんH、五ほんH、六ぽんP、七ほんH、八ぽんP、九ほんH、十ぽんP、…と続きます。例外もありますが、変化するハ行の助数詞は、P、H、B、・「一匹、二匹、三匹、…」も同様に変化します。 日本語教育の初級では、数字の読み方、カレンダーの読み方、時計の読み方、さらに助数詞と勉強しますから、留学生は覚えるだけでも大変です。よほど面白く教えないと、この段階でつまずいてしまい、「先生、全部”こ”でいいですか?」と聞いてきます。 また、日本語でよく使う表現に「動詞+”いる”」「動詞+”くる”」などの「てフォーム(て・form)」があります。「買っている」とは言いますが「買ている」とは言いません。「来ている」とは言いますが、「来っている」と言いません。留学生が「なぜ、こう変化するの?」と日本人に聞いても答えられないでしょう。 「買う」「持つ」「売る」などの”う”、”つ””る”で終わる動詞は「買って」「持って」「売って」のように”って”となり、「生む」「遊ぶ」「死む」などの”む”、”ぶ”、”ぬ”で終わる動詞は「生んで」「遊んで」「死んで」と ”んで”となります。 -普段、あまり考えたことのない日本語のルールですね。 日本にいる日本人の子どもは、生まれてからずっと日本語を聞き、話し、脳の言語中枢に日本語の使い方がしみ込んでいますので、日本人は、話すことができれば日本語のルールについて理解していると思って、小学校でも中学校でも国語教育でこういうことを教えていません。ですから、もっと読者の方に、母語である日本語のルールを知っていただければなと思っております。 普段、意識していない表現で、指導の難しいものはたくさんあります。例えば、〝~おきに〟という場合、「一時間おきにバスが出る」は、一時にバスが出たら次のバスは二時に出ます。その次は三時。でも、黒と白の石があって、「黒の石を一個おきに置く」場合、黒、白、黒、白、…なら一番目、三番目、五番目…が黒ですね。日本語の”~おきに” は、英語の”every~”と”every other~”の場合があるのです。 -そう言われればそうですね。 ご者書『日本語を「外」から見る』(小学館新書)を拝読しましたが、物語としても素晴らしく、日本語の森の中に足を踏み込んでいくようで、もう一度日本語を学んでみたいという思いがいたしました。 ありがとうございます。あの本は、体験をもとに、留学生たちとの日本語教室での交流、日本語の特徴や文法について描きました。きっと読者のみなさんも、一緒に考えていただけるのではないでしょうか。 日本語を教えるときは、会話の場面をしっかり設定して例文を指導することで、学んだ日本語を日常のコミュニケーションで活かすことができるようにしています。私の日本語の授業では、文法は骨格であり、骨格の上に楽しい会話・自然な会話を学んでもらうことを目標にしています。 今、作文力や読解力の低下が心配です。文章に接するのはメールやツイッターがほとんどで、短い文章しか書けない・読めない人が増えています。人は、考えをまとめたり感情を表現するとき、言葉を使います。言葉はコミュニケーションに必要なものです。子どもが興味の持てるゲームや言葉遊びを中心に授業を進めていけば、国語の時間が楽しくなって、子どもは国語が好きになりますよね。 また、言葉にはプラスのイメージを持つものとマイナスのイメージを持つものがあります。震災で福島から避難してきている子どもに、先生まで名前に「菌」を付けて呼んだといういじめの事件がありました。 「ばい菌」 の「菌」 ですから、どれだけその子が傷ついたかと思うといたたまれない思いです。先生が、「頑張り屋の○○さん」とプラスのイメージを持つ言葉でその子を呼んであげれば、とっても励まされると思うんですよ。私もクラスに馴染めていない留学生を「笑顔の○○さん」などとプラスイメージのニックネームで呼ぶようにしていました。 -”ほっこり”言葉と”ちくちく”言葉ですね。 子育て中のお母さんたちの親子教室で話を伺いましたら、今、辛い思いをされている方がけっこう多くて、「こんにちは」って挨拶してもらったり、「昨日は寒かったですね」と声がけしてもらうだけで、うれしいと言うんですね。そして、「何よ、一人だけ」とか「ちょっと変わっているんだから」と聞こえると、傷つくと。 夫に子どもを預けなければ出かけられない人が集合時間に遅れてきたとき、周りの人が「あの人、いつも遅いんだから」ではなく、「お父さんが帰ってきて、来られて良かったね」と言えば、気持ちが明るくなります。お母さんたちにマイナスからプラスへの転換方法を学んでもらうために、「あなたのおかげで」で文章を作ってもらいました。「~のせいで」と「~のおかげで」は意味が似ていても、「~のおかげで」は「あなたのおかげで成功した」のようにプラスのイメージです。そうしたら、教室にご参加のみなさん、楽しそうでした。 「どう話すか」 は、とっても大事です。こちら(インタビューの場所)に来る電車で、お母さんと小さな子どもが隣に座っていたのですが、お母さんの言葉が命令形なんです。「靴をぬぎなさい!」「立っちゃダメ!」…。命令形を使わないで、子どもに伝えるためには、どうすればいいと思いますか? 「靴、脱ごうか?」と疑問形で話すと、子どもが「どうして?」と聞いてきたら、「だって、座席が汚れちゃうじゃない」と説明すればいいですね。そこにコミュニケーションが成立するし、命令されて行動するのではなく、一緒に考えて行動する子どもが育ちます。 認知症の方の場合、コミュニケーションの取り方一つで雰囲気が変わります。介護をする方が命令形で話す施設では入所者や患者さんが怯えた顔をされていますし、疑問形で「寒くない?布団かけましょうか?」などのように話しかけをしている施設では柔和な顔をされています。 -人権擁護委員が開催する人権教室の題材になると感じました。 二〇〇〇(平成十二)年に、日本語ジェンダー学会を立ち上げられたとのことですが、どういうきっかけで、日本語の中のジェンダーの研究をはじめられたのですか。 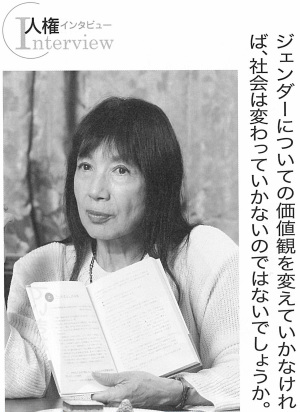 私の初めてのジェンダーに関する論文は四十代で書きましたけれども、内容は、終助詞についてです。終助詞は、主に文の終わりに付いて、話し手から聞き手への伝達に伴う態度や気持ちを表します。「~ですね」 の”ね”がそうです。 あるときテレビドラマでお父さん役の俳優さんが「おい、行くぞ」と言うのを聞いて、二人の娘たちが真似をして「おい、行くぞ」。「あなたたちは、”行くぞ”と言っちゃダメ」と注意すると「どうして?」と聞かれ、「〝行くぞ〟は男の人の言い方だから、女の人は使ってはいけないの」と答えたら、「そんなの不公平だ」と言うんですね。 「行くわ」は優しく聞こえる言い方で、女の人が使います。「行くよね」は同意を求める感じ、「行くよ」は相手に主張していて、女の人も男の人も使い、「行くぞ」は命令調で、男の人が使います。こんなところにも「女」と「男」があり、当事者の力関係まで明らかになると気づき、興味を持って調べるようになったのが始まりです。 例えば、男子サッカーチームは「サムライジャパン」、女子サッカーチームは「なでしこジャパン」のように男性だけ、女性だけに使う言葉もありますね。 「サムライ」は、強くて正義感のある男性というイメージで、男性のスポーツ選手などをたたえるときによく使われますが、女性にも強くド正義感のある人がいます。また、病弱で気が弱いけれど、人間味のある優しさを兼ね備えた男性も多くいます。 ジェンダーは、社会的・文化的に作られた「男らしさ」「女らしさ」です。ジェンダー表現には、社会の中での男性や女性に対する見方や価値観といったものが含まれていて、あるべき姿を強制しているものがあるように感じます。「女性活躍社会を推進する」と言っても、価値観を変えていかなければ、社会は変わっていかないのではないでしょうか。 -確かにそうですね。 最近は、あまり使われなくなりましたが、OL-オフィス・レディという言葉は、女性が男性の添え物であるような感じがします。 OLは、和製英語で、一九六三年、東京オリンピックの前年に女性週刊誌『女性自身』が一般公募して使われるようになった言葉です。 戦前・戦後を通して、働く女性は「職業婦人」と呼ばれていましたが、一九五〇年代後半の高度成長期に入り、女性の事務職にはBG(ビジネスガール)という名称が使われるようになりました。しかしアメリカ英語では、BG-バーガール(bar girl)には売春婦という意味もあることから、NHKが使用禁止を決めました。それで、一般公募で生まれたのがOLです。 今「OL」と言うと、何歳ぐらいの女性を想定されますか?四十代で働く女性をOLと言いますか7 -四十代前半で、ぎりぎりぐらい……。 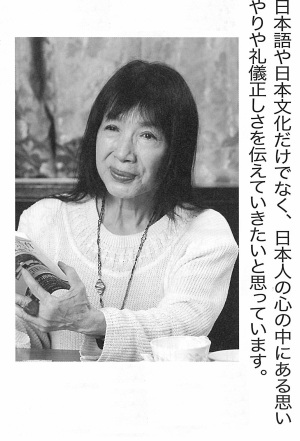 二十代、三十代ぐらいのイメージですよね。男女の役割分業で「男は外で働くもの」「女は家の中にいるもの」という概念が基本にあって、結婚するのが前提で、それまで腰掛的に働いている人という意味があったんですよ。 ですから「OL」だと、どんな仕事をしているか、専 門的な仕事をしていても、外部からは分かりません。男性上司がいてその命令系統の下に働く、どちらかと言えば「若い事務職の女性で、専門職ではない人」という概念ができ上がってしまっています。 「OL」という言葉が使われなくなったのは、女性の専門職が徐々に増えてきて「キャリアウーマン」という言葉が使われるようになり、女性が自信を持つようになってきた証だと思います。時代の変化によって言葉も変わってくる一つの典型例です。 -その意味では、「イクメン」 は楽しみな言葉ですね。 いい言葉ですよね。 最初、男の人は「イクメン」と言われると嫌だったそうです。でも、今、「イクメン」と呼ばれると誇らしいと言います。以前は「保育園に迎えに行くので早退します」と 言いにくかったのが、今は「イクメンなも んで」とか「今日、定時退社します」と言うと「いいなあ。お前のところは子どもがいて」という反応なんだそうです。社会の変化は確実に表れていて、お父さんと子どもだけで堂々と買い物に行くし、「お父さんのための料理教室」は盛況です。 「イクメン」は「イケメン」 の語呂合わせてできた言葉のようです。「育」-「育てる」の音読みと英語の「メン」-「男」を合わせたところがカッコイイと思うんです。日本語は外来語をミックスすることで新しい言葉を作ることができます。私は、造語作用があると言っているんですけれど、造語作用で、こういう日本語がどんどんできるといいと思っています。留学生には、ジェンダー表現を通しても日本や日本人についての理解を深めてもらってきました。 -留学生に、いわゆる日本語の使い方だけでなく、生きた言葉を指導される。すごいことですね。 私は、最初は英語の先生だったんです。日本大学の国際関係学部で英語翻訳法を教えていて、文法の間違いは指摘できるんですけれど、英語が持つ言葉としてのニュアンスの違いが分からないのに学生に指導することは欺瞞ではないかと思うようになりました。そういうときに、「横田基地に住む将校夫人クラブの人たちに、日本語を教えてくれませんか」という依頼をいただきました。日本語ができなくて、買い物にも行けなくて不便をされていたのです。 四十年くらい前ですから、当時は「日本語教育」が一般的でない時代で、日本語の指導を手さぐりで始めるようになりました。毎週、「買い物編」「旅行編」「電話の掛け方編」…とサバイバルジャパニーズを英語で教えていく中で、日本語はルールがありすぎて教えにくいと気づきました。 その後、調布のアメリカン・スクール・イン・ジャパンで日本語の先生をする機会があり、そこで初めてハワイ大学で出している日本語のテキストを見たんです。「英語で、こういう本があるんだ」と驚きました。最初にご紹介した「てフォーム」-”って”と”んで”など、日本人が気づかなかった日本語のルールがたくさん書いてありました。 アメリカは”戦勝国”ですよね。ベネディクトの『菊と刀』もそうですが、日本についてよく研究しています。日本文学者のドナルド・キーンさんと函館のシンポジウムでご一緒したことがあって、キーンさんに「日本語をどうやって覚えたんですか」とお聞きしたら、「僕は元々海兵隊で、潜水艦の前も後ろも分からなかったけれど、毎日、日本語漬けだった」とおっしゃっていました。戦争中に敵国の言葉を勉強していたのですよ。言葉を理解することで相手の国民性を理解しょうとする、日本が「敵国語」である英語使用を禁止していたのとは逆の発想です。 -最後に、人権のひろばの読者の方々にメッセージをお願いします。 二〇二年三月十一日、東日本大震災が発生し、津波によって家を流された、家族を流された、…悲惨な状況が次々にテレビに映し出されていた中、アメリカのニュースでは「これほどの被害に遭いながらも、日本人はパニックに陥らず、秩序を保ち、礼儀さえ保ってお互いに助け合っている」と報道されたそうです。 研究室で留学生たちと一緒にニュースを見ていましたが、留学生たちは、日本語や日本文化だけでなく、日本人の心の中にある思いやりや礼儀正しさを大切にする心も感じ取ってくれていました。 昨年は熊本でも震災があり、被災地にはまだまだ大変な思いをされている方々がたくさんいらっしゃいます。いち早い復興を願うとともに、日本語教育を通して、日本人の心を伝えていきたいと思っています。 -言葉の力は大きいですね。 興味深いお話をありがとうございます。ますますのこ活躍を願っています。 (次回は作曲家・聖川湧氏の予定です) |
|
プロフィール/ささき・みずえ |