2017年11月
平成30年度高等学校国語科教科書指導書付属DVD-ROM(東京書籍)に掲載
敬語は難しい? 『日本語を「外」から見る』
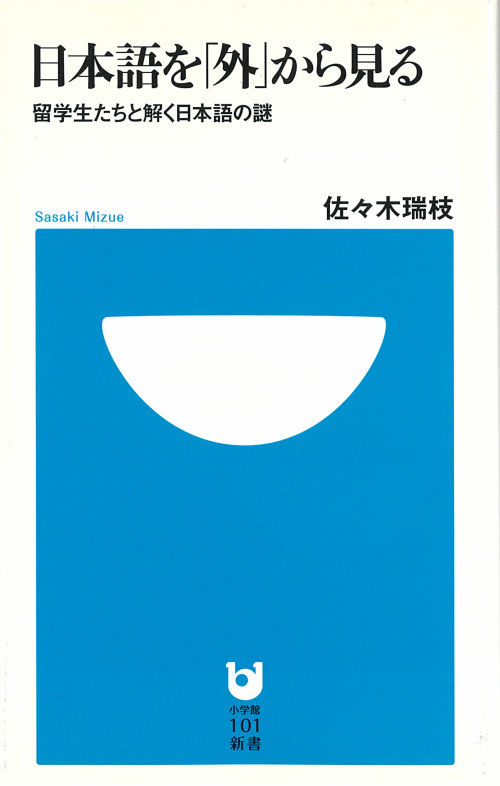
| 9 敬語は難しい? 国際村の銀杏並木が美しい黄色に染まり、コスモスの花が風に揺れている。留学生たちも秋の風に里心がつくのだろうか。風に乗って、「コンドルは飛んでいく」の物悲しいアンデスの音楽が聞こえてくる。あれはペルーのジョセフ君の部屋だろうか。部屋のドアは開け放たれ、音楽は湘南の風に乗って遠く遠く流れていく。 音楽の源をたどって、ジョセフ君の部屋に。壁にはアンデスの山々の写真や家族の写真が二面に貼られ、まるで彼の故郷への思いを募らせているかのようだ。 家族はスペイン風の家具のある居間で、にっこり微笑んでいる。黒いタキシード姿はお父さんだろうか。ジョセフ君は「征服民族スペイン人」との混血だという。 「先生、僕はユールシを家族に送りたいのですが」とジョセフ君。 「ユールシ? それは何ですか」 「えっ、先生おシリになりませんか。日本の代表的な芸術品なのに」 ユールシは何かを頭の中でイメージしている。しかし、何のことやらまったく見当がつかない。「お知りになりませんか」とジョセフ君に言われると「ユールシ」を知らない私がちょっと恥ずかしい。そんなもの、日本にありましたっけ。 しかし「お知りになりませんか」は簡単に敬語の誤用だと分かる。「お……になる」、つまり「考える-お考えになる」などと同様の文型パターンから「知る-お知りになる」となったのだろう。ジョセフ君がアンデスの音楽の中で話すと、まるで「これぞ正しい敬語」のように聞こえてくるから不思議だ。管楽器ケーナが短調のメロディーをゆっくりと奏でている。 もう一度、フォルクローレを聞きながら「敬語」 の授業を振り返ってみよう。 授業では次のように指導した。 「持つ-お持ちになる。-傘をお持ちになりましたか。明日は天気予報で雨が降るようですから-尊敬表現」 「持つ-お持ちする。-先生、重そうですね。荷物を駅までお持ちしましょうか-謙譲表現」 「お-になる」は、「動詞」を、尊敬語のパターンで使おうとする時一番無難な方法で、留学生にも指導しやすい。敬語を指導するときにパターン化されたスタイルをここに書き出してみよう。 「ご-になる ご覧になる ご+漢語」 「お-なさる お話しなさる」 「ご-なさる ご卒業なさる ご+漢語+なさる」 「お-くださる お読みくださる」 「ご-くださる ご入場ください」 (文法的には形式動詞と言われるもの) ジョセフ君は話し相手の私を気遣い、いつも敬語を使ってくれるのだが、今日の「お知りになる」のように、残念なことにミスが多い。この場合は「ご存じありませんか」が正しい使い方だが、日本人でも、「先生、知りませんか」などと平気で言う学生も多く、留学生の敬語の間違いをいちいち直すべきか、それとも黙って微笑むべきか、それが問題だ。今田は素敵な音楽の中で日本語の授業の延長も無粋だ。それよりも「ユールシ」の方の問題解決を先行させることにしよう。 「ユールシはどんな時に使いますか。どんなものですか」、これでは、私が留学生のようだ。 「ええと、古い食器やお箸、それに箱などに使います。あっ、女性の櫛も見たことがあります」 ジョセフ君の説明を聞くうちに、ユールシが漆のことだと分かった。なるほど、漆ですか。確かに、「漆」をローマ字で書くとURUSHH、よくある間違いのパターンだ。 「私、来週金沢で学会があるので、何か買ってきてあげましょうか。それほど重くないもの」。漆と言えば輪島塗だけど、いくらジョセフ君が文科省から奨学金を支給されているとはいえ、彼の懐具合も考えて、輪島塗のお箸か何か買ってきてプレゼントするとしよう。 研究室で北陸のガイドブックを広げていたら、向かい側の部屋のコンピュータを使い終わった留学生たちが、通りすがりに部屋をのぞき込む。ガイドブックを広げているところから旅行の計画と思ったのだろう、「どこかに旅行に行くのですか。私たちも参ります」と言う。 そう言えば、彼らと旅行の約束をしながらまだ果たしていない。晩秋になると、北陸の風は冷たいかもしれないが、日本海を見せるのもいいかもしれない。それにしても、「私たちも参ります」とはかなり断定的な使い方だ。聞き手が私だから良いものの、他の先生だったら、この使い方に対してどう思われるだろうか。「連れていってください」と言いなさいとでもおっしゃるだろうか。 尊敬語・謙譲語の指導では形式動詞とは別に、次のものは指導しておく。 ■留学生に教えておきたい動詞の尊敬語 ①いらっしゃる(来る、行く、いる) 今度金沢にいらっしゃるのですか。(行く) ペルーの私の家にいらっしゃいませんか。(来る) 明日、午前中、研究室にいらっしゃいますか。(いる) ②おっしゃる (言う) 先生がおっしゃることはよくわかります。しかし…。 ③なさる (する) そんなことなさっては、お疲れになりますよ。 ④めしあがる (食べる) よろしかったら、めしあがってください。 日本語の動詞で、これらのように尊敬語が定型化したものの数は多くはない。 ジョセフ君のように、たとえ、使い方を間違えたとしても、そこに敬意の意識が感じられれば有り難いと思う。日本人はそのくらいの感覚で留学生の日本語の間違いを、鷹揚に受け止めて欲しいと思う。敬語は他者中心的な日本文化の現れであり、むしろ、直してもらうべきは、自己中心的で敬意意識のない日本の若者たちなのだから。 |