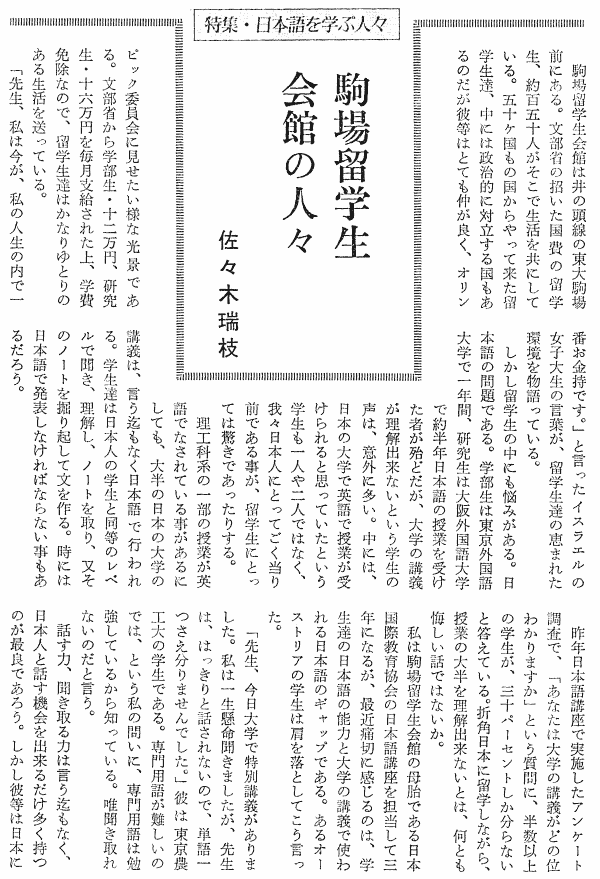
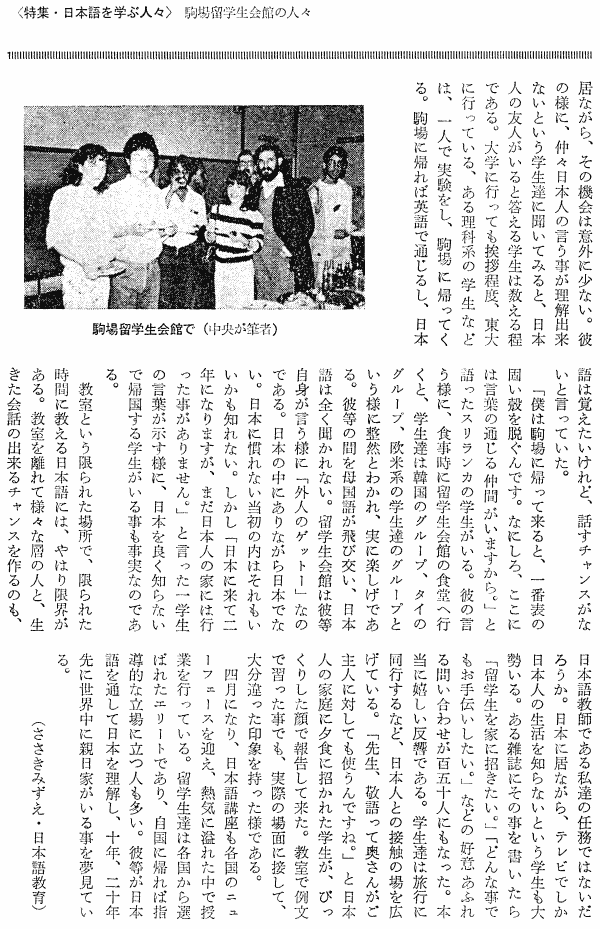
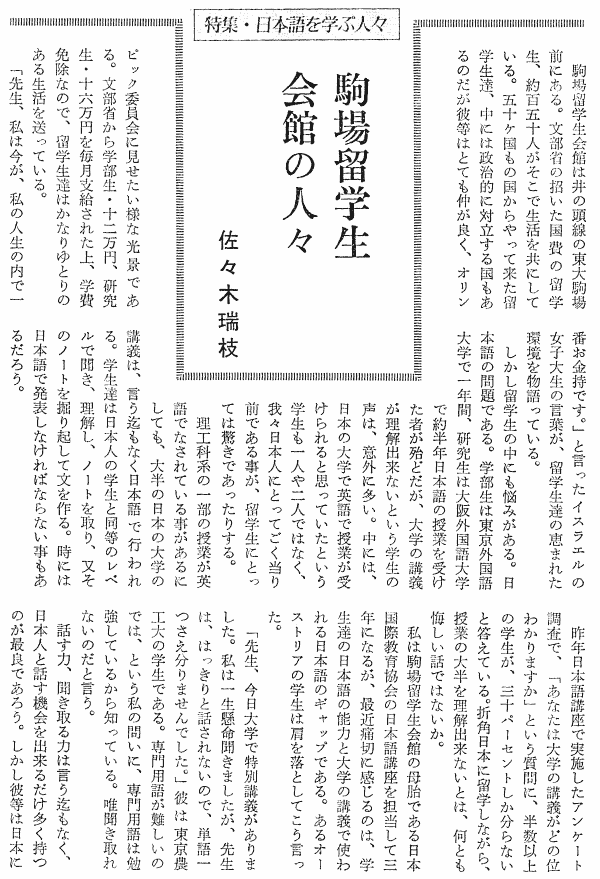
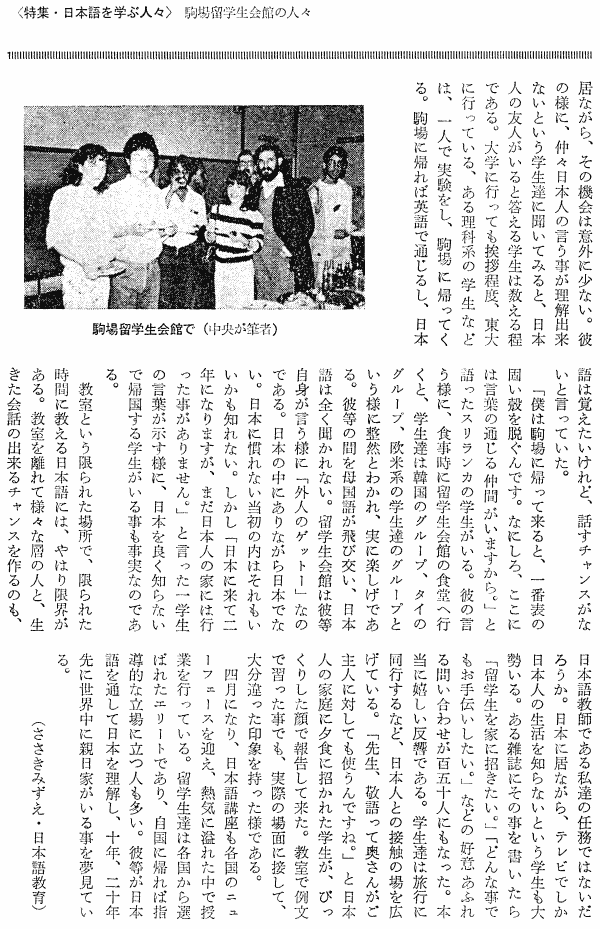
|
駒場留学生会館の人々
佐々木瑞枝 駒場留学生会館は井の頭線の東大駒場前にある。文部省の一招いた国費の留学生、約百 五十人がそこで生活を共にしている。五十ケ国もの国からやって究た留 学生達、中には政治的に対立する国もあるのだが彼等はとても仲が良く、オリンピック委員会に見せたい様な光景である。文部省から学部生・十二万円、研究 生・十六万円を毎月支給された上、学費免除なので、留学生達ほかなりゆとりのある生活を送っている。 「先生、私は今が、私の人生の内で一番お金持です。」と言ったイスラエルの女子大生の言葉が、留学生達の恵まれた環境を物語っている。 しかし留学生の中にも悩みがある。日本語の問題である。学部生は東京外国語大学で一年間、研究生は大阪外国語大学で約半年日本語の授業を受けた者が殆ど だが、大学の講義が理解出来ないという学生の声は、意外に多い。中には、日本の大学で英語で授業が受けられると思っていたという学生もー人や二人ではな く、我々日本人にとってごく当り前である事が、留学生にとってほ驚きであったりする。 理工科系の一部の授業が英語でなされている事があるにしても、大半の日本の大学の講義は、言う迄もなく日本語で行われる。学生達ほ日本人の学生と同等の レベルで聞き、理解し、ノートを取り、又そのノートを掘り起して文を作る。時にほ日本語で発表しなければならない事もあるだろう。 昨年日本語講座で実施したアンケート調査で、「あなたほ大学の講義がどの位わかりますか」という質問に、半数以上の学生が、三十パーセントしか分らない と答えている。折角日本に留学しながら、授業の大半を理解出来ないとほ、何とも悔しい話でほないか。 私ほ駒場留学生会館の母胎である日本国際教育協会の日本語講座を担当して三年になるが、最近痛切に感じるのほ、学生達の日本語の能力と大学の講義で使わ れる日本語のギャップである。あるオーストリアの学生は肩を落としてこう言った。 「先生、今日大学で特別講義がありました。私ほ一生懸命聞きましたが、先生は、はっきりと話されないので、単語一つさえ分りませんでした。」彼ほ東京農 工大の学生である。専門用語が難しいのでは、という私の問いに、専門用語は勉強しているから知っている。唯聞き取れないのだと言う。 話す力、聞き取る力は言う迄もなく、日本人と話す機会を出来るだけ多く持つのが最良であろう。しかし彼等は日本に居ながら、その機会ほ意外に少ない。彼 の様に、仲々日本人の言う事が理解出来ないという学生達に聞いてみると、日本人の友人がいると答える学生は数える程である。大学に行っても挨拶程度、東大 に行っている、ある理科系の学生などは、一人で実験をし、駒場に帰ってくる。駒場に帰れば英語で通じるし、日本語は覚えたいけれど、話すチャンスがないと 言っていた。 「僕は駒場に帰って来ると、一番表の固い殻を脱ぐんです。なにしろ、ここには言葉の通じる仲間がいますから。」と語ったスリランカの学生がいる。彼の言 う様に、食事時に留学生会館の食堂へ行くと、学生達は韓国のグループ、タイのグループ、欧米系の学生達のグループという様に整然とわかれ、実に楽Lげであ る。彼等の間を母国語が飛び交い、日本語は全く聞かれない。留学生会館は彼等自身が言う様に「外人のゲットー」なのである。日本の中にありながら日本でな い。日本に慣れない当初の内はそれもいいかも知れない。しかし「日本に来て二年になりますが、まだ日本人の家には行った事がありません。」と言った一学生 の言葉が示す様に、日本を良く知らないで帰国する学生がいる事も事実なのである。 教室という限られた場所で、限られた時間に教える日本語には、やはり限界がある。教室を離れて様々な層の人と、生きた会話の出来るチャンスを作るのも、 日本語教師である私達の任務ではないだろうか。日本に居ながら、テレビでしか日本人の生活を知らないという学生も大勢いる。ある雑誌にその事を書いたら 「留学生を家に招きたい。」「どんな事でもお手伝いしたい。」などの好意あふれる問い合わせが百五十人にもなった。本当に嬉しい反響である。学生達は旅行 に同行するなど、日本人との接触の場を広げている。「先生、敬語って奥さんがご主人に対しても使うんですね。」と日本人の家庭に夕食に招かれた学生が、 びっくりした顔で報告して来た。教室で例文で習った事でも、実際の場面に接して、大分違った印象を持った様である。 四月になり、日本語講座も各国のニューフェースを迎え、熱気に溢れた中で授業を行っている。留学生達ほ各国から選ばれたエリートであり、自国に帰れば指 導的な立場に立つ人も多い。彼等が日本語を通して日本を理解し、十年、二十年先に世界中に親日家がいる事を夢見ている。 (ささきみずえ・日本語教育)
|