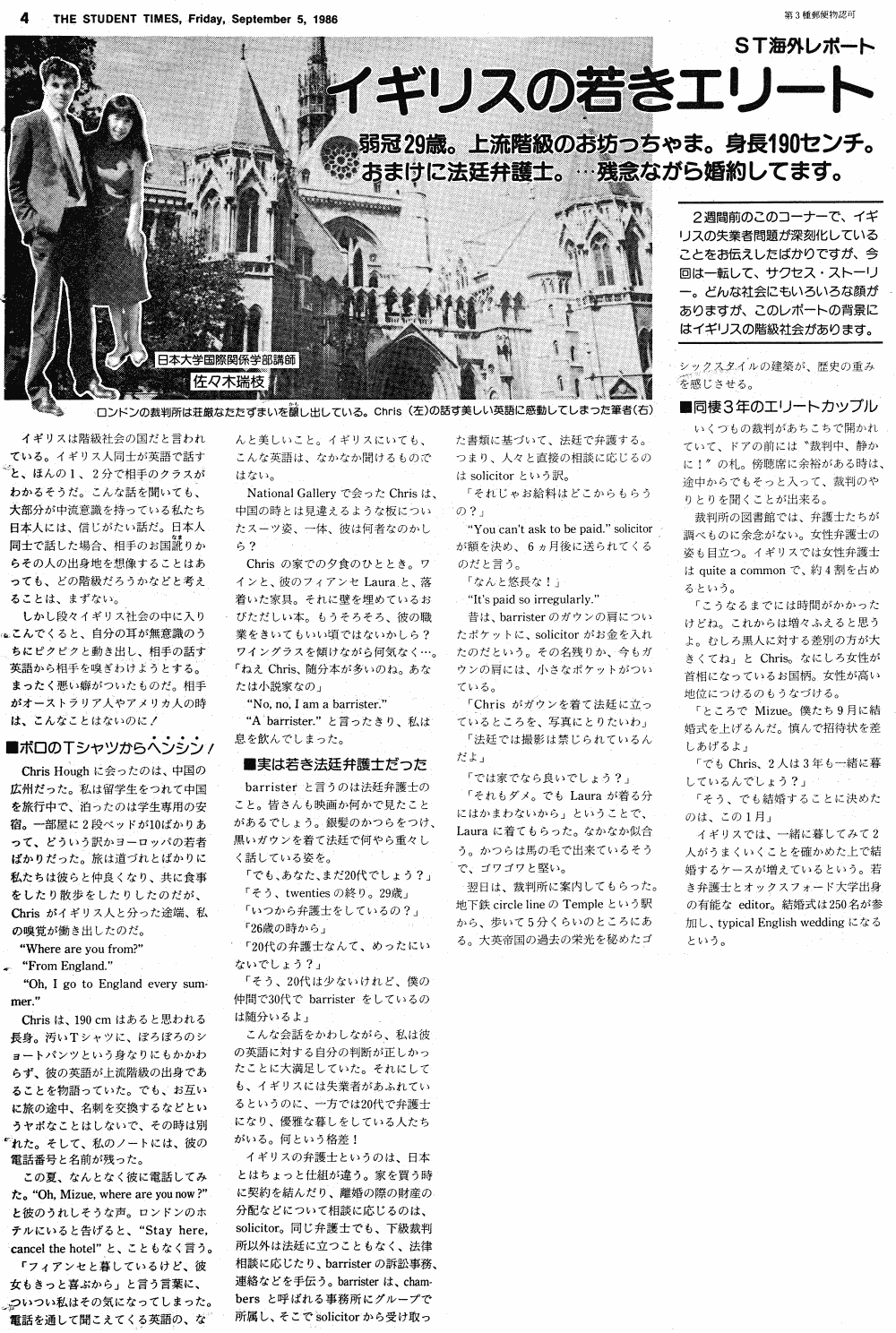
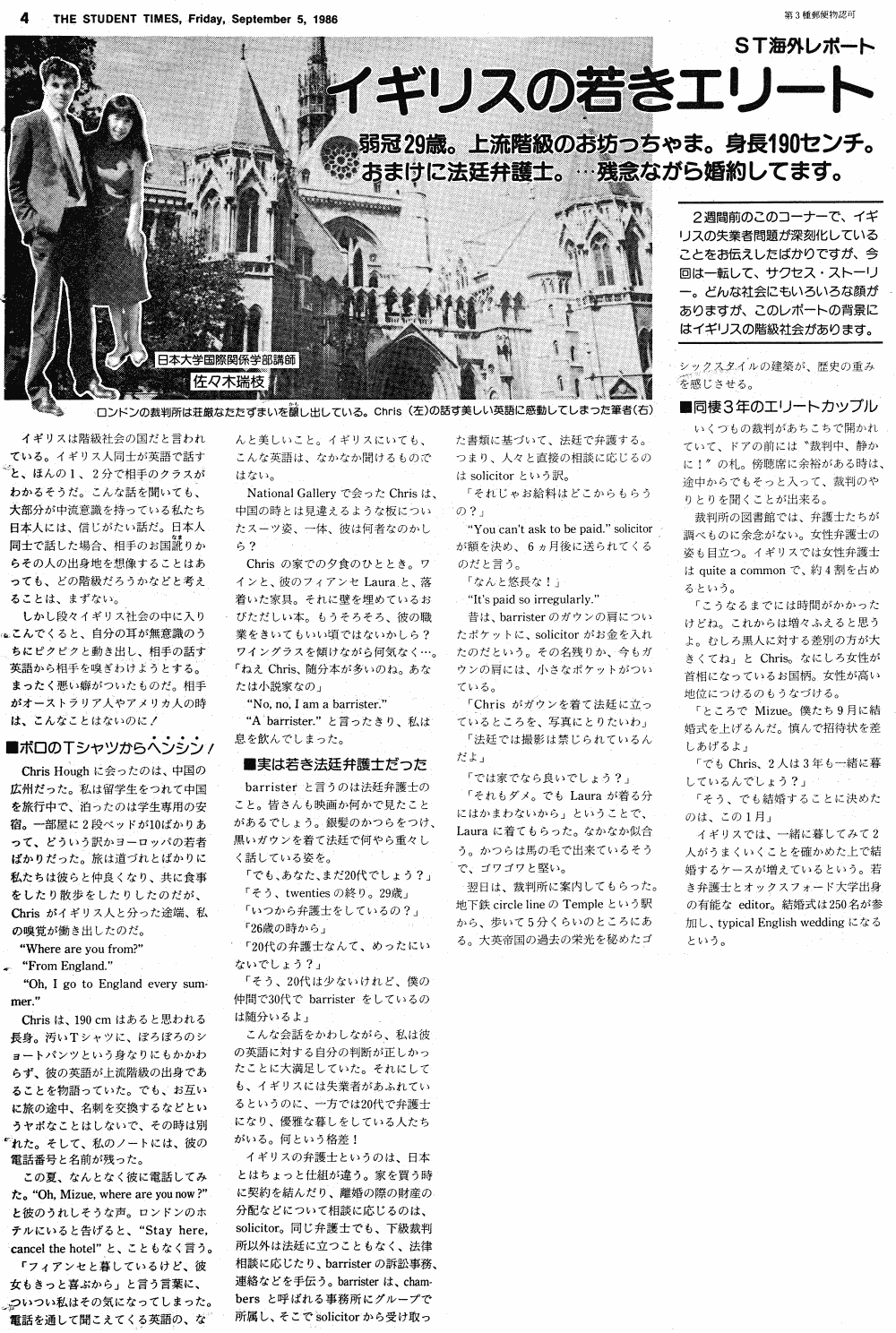
|
イギリスの若きエリート。若干29歳。上流階級のお坊ちゃま。身長190センチ。 おまけに法廷弁護士。・残念ながら婚約してます。 ロンドンの裁判所は荘厳なたたずまいを醸し出している。Chris(左)の話す美しい英語に感動してしまった筆者(右) 2週間前のこのコーナーで、イギリスの失業者問題が深刻化していることをお伝えしたばかりですが、今回は一転して、サクセス・ストーリー。どんな社会にもいろいろな顔がありますが、このレポートの背景にはイギリスの階級社会があります。 イギリスは階級社会の国だと言われている。イギリス人同士が英語で話すと、ほんの1、2分で相手のクラスかわかるそうだ。こんな話を聞いても、大部分が中流意識を持っている私たち日本人には、信じがたい話だ。日本人同士で話した場合、相手のお国訛りからその人の出身地を想像することはあっても、どの階級だろうかなどと考えることは、まずない。 しかし段々イギリス社会の中に入りこんでくると、自分の耳が無意識のうちにピタピクと動き出し、相手の話す英語から相手を嗅ぎわけようとする。まったく悪い癖がついたものだ。相手がオーストラリア人やアメリカ人の時は、こんなことはないのに! ■ポロの丁シャツからヘンシン! Chris Houghに会ったのは、中国の広州だった。私は留学生をつれて中国を旅行中で、泊ったのは学生専用の安宿。一部屋に2段ベッドが10ばかりあって、どういう訳かヨーロッパの若者ばかりだった。旅は道づれとばかりに私たちは彼らと仲良くなり、共に食事をしたり散歩をしたりしたのだが、Chrisがイギリス人と分った途端、私の喚覚が働き出したのだ。 “Whereareyoufrom?” ”FromEngland.” ”Oh,I go to England every summer.” Chrisは、190cmはあると思われる長身。汚いTシャツに、ぼろぼろのショートパンツという身なりにもかかわらず、彼の英語が上流階級の出身であることを物語っていた。でも、お互いに旅の途中、名刺を交換するなどというヤボなことはしないで、その時は別これた。そして、私のノートには、彼の電話番号と名前が残った。 この夏、なんとなく彼に電話してみた。“Oh,Mizue,Where are you now?”と彼のうれしそうな声。ロンドンのホテルにいると告げると、“Stay here,Cancel the hotel"と、こともなく言う。 「フィアンセと暮しているけど、彼女もきっと喜ぶから」と言う言葉に、置いつい私はその気になってしまった。電話を通して聞こえてくる英語の、なんと美しいこと。イギリスにいても、こんな英語は、なかなか聞けるものではない。 National Galleryで会ったChrisは、中国の時とは見違えるような板についたスーツ姿、一体、彼は何者なのかしら? Chrisの家での夕食のひととき。ワインと、彼のフィアンセLaura.と、落着いた家具。それに壁を埋めているおびただしい本。もうそろそろ、彼の職業をきいてもいい頃ではないかしら? ワイングラスを傾けながら何気なく・・・。「ねえChris、随分本が多いのね。あなたは小説家なの」 “No,no,l am abarrister.” “A barrister.”と言ったきり、私は息を飲んでしまった。 ■実は若き法廷弁護士だった barristerと言うのは法廷弁護士のこと。皆さんも映画か何かで見たことがあるでしょう。銀髪のかつらをつけ、黒いガウンを着て法廷で何やら重々しく話している姿を。 「でも、あなた、まだ20代でしょう?」 「そう、twentiesの終り。29歳」 「いつから弁護士をしているの?」 「26歳の時から」 「20代の弁護士なんて、めったにい ないでしょう?」 「そう、20代は少ないけれど、僕の仲間で30代でbarristerをしているのは随分いるよ」 こんな会話をかわしながら、私は彼の英語に対する自分の判断が正しかったことに大満足していた。それにしても、イギリスには失業者があふれているというのに、一方では20代で弁護士になり、優雅な暮しをしている人たちがいる。何という格差! イギリスの弁護士というのは、日本とはちょっと仕組が違う。家を買う時に契約を結んだり、、離婚の際の財産の、分配などについて相談に応じるのは、solicitor。同じ弁護士でも、下級裁判所以外は法廷に立つこともなく、法律相談に応じたり、barristerの訴訟事務、連絡などを手伝う。barristerは、Chambers と呼ばれる事務所にグループで所属し、そこで義solicitorから受け取った書類に基づいて、法廷で弁護する。つまり、人々と直接の相談に応じるのはsolicitorという訳。 「それじゃお給料はどこからもらうの?」 “You can't ask to be paid.”solicitorが額を決め、6ヵ月後に送られてくるのだと言う。 「なんと悠長な!」 “It's paid so irregularly." 昔は、barristerのガウンの肩についたポケットに、solicitorがお金を入れたのだという。その名残りか、今もガウンの肩には、小さなポケットがついている。 「Chrisがガウンを着て法廷に立ちいるところを、写真にとりたいわ」 「法廷では撮影は禁じられているんだよ」 丁では家でなら良いでしょう?」 「それもダメ。でも Lauraが着る分にはかまわないから」ということで、Lauraに着てもらった。なかなか似合う。かつらは馬の毛で出来ているそうで、ゴワゴワと堅い。 翌日堕、裁判所に案内してもらった。 地下鉄circle lineのTempleという駅から、歩いて5分くらいのところにある。大英帝国の過去の栄光を秘めたゴシックスタイルの建築が、歴史の重みを感じさせる。 ■同棲3年のエリートカップル いくつ ̄もの裁判があちこちで開かれていて、ドアの前には“裁判中、静かに!〝の札。傍聴席に余裕がある時は、途中からでもそっと入って、裁判のやりとりを聞くことが出来る。 裁判所の図書館では、弁護士たちが調べものに余念がない。女性弁護士の姿も目立つ。イギリスでは女性弁護士はquite a commonで、約4割を占めるという。 「こうなるまでには時間がかかったけどね。これからは増々ふえると思うよ。むしろ黒人に対する差別の方が大きくてね」と Chris。なにしろ女性が首相になっているお国柄。女性が高い地位につけるのもうなづける。 「ところでMizue。僕たち9月に結婚式を上げるんだ。慎んで招待状を差しあげるよ」 「でこもChris、2人は3年も「緒に暮しているんでしょう?」 「そう、でも結婚することに決めたのは、この1月」 イギリスでは、一緒に暮してみて2人がうまくいくことを確かめた上で結婚するケースが増えているという。若き弁護士とオックスフォード大学出身の有能なeditor。結婚式は250名が参加し、typical English weddingになるという。 |