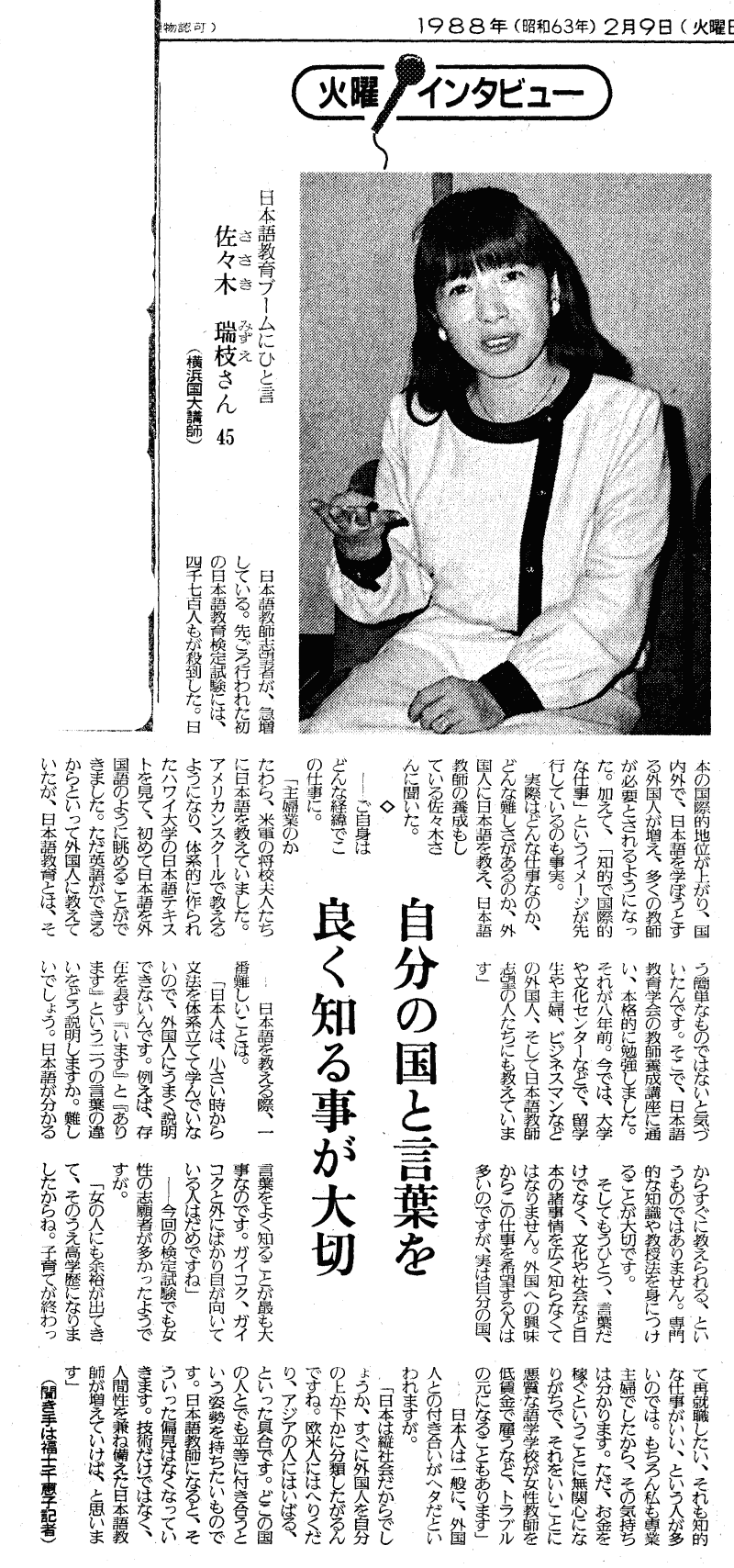
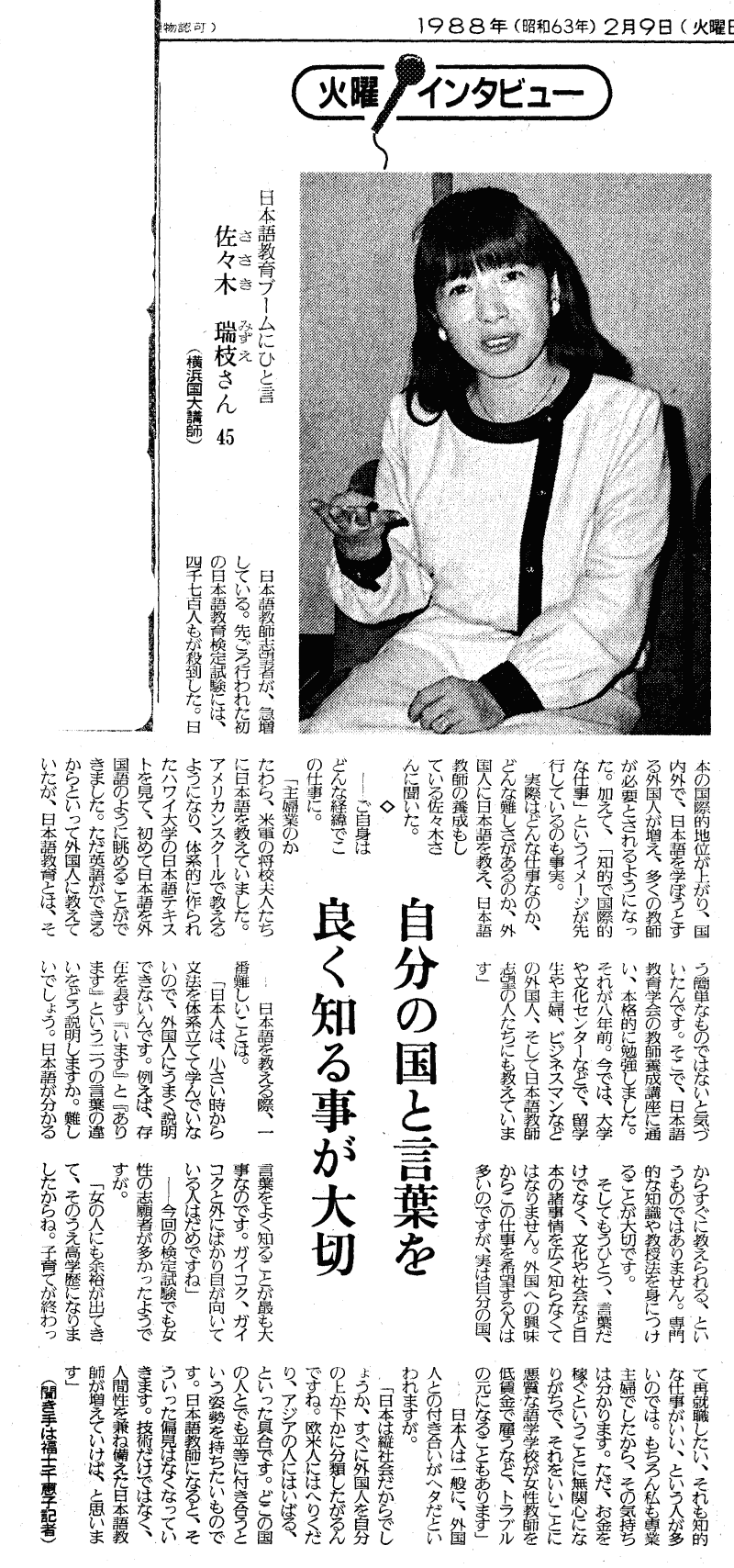
| 火曜インタビュー 日本語教育ブームにひと言 佐々木瑞枝(ささきみずえ)さん45(横浜国大講師) 自分の国と言葉を良く知ることが大切 日本語教師志望者が、急増している。先ごろ行われた初の日本語教育検定試験には、四千七画人もが殺到した。日本の国際的地位が上がり、国内外で、日本語を学ぼうとする外国人が増え、多くの教師が必要とされるようになった。加えて、「知的で国際的な仕事」というイメージが先行しているのも事実。 実際はどんな仕事なのか、どんな難しさがあるのか、外国人に日本語を教え、日本語教師の養成もしている佐々木さんに聞いた。 ◇ ―ご自身はどんな経緯でこの仕事に。 「主婦業のたわら、米軍の将校夫人たちに日本語を教えていました。アメリカンスクールで教えるようになり、体系的に作られたハワイ大学の日本語テキストを見て、初めて日本語を外国語のように眺めることができました。ただ英語ができるからといって外国人に教えていたが、日本語教育とは、そう簡単なものではないと気づいたんです。そこで、日本語教育学会の教師養成講座に通い、本格的に勉強しました。それが八年前。今では、大学や文化センターなどで、留学生や主婦、ビジネスマンなどの外国人、そして日本語教師志望の人たちにも教えています」 ―日本語を教える際、一番難しいことは。 「日本人は、小さい時から文法を体系立てて学んでいないので、外国人にうまく説明できないんです。例えば、存在を表す『います』と『あります』という二つの言葉の違いをどう説明しますか。難しいでしょう。日本語が分かるからすぐに教えられる、というものではありません。専門的な知識や教授法を身につけることが大切です。 そしてもうひとつ、言葉だけでなく、文化や社会など日本の諸事情を広く知らなくてはなりません。外国への興味からこの仕事を希望する人は多いのですが、実は自分の国、言葉をよく知ることが最も大事なのです。ガイコク、ガイコクと外にばかり目が向いている人はだめですね」 ―今回の検定試験でも女性の志願者が多かったようですが。 「女の人にも余裕が出てきて、そのうえ高学歴になりましたからね。子育てが終わって再就職したい、それも知的な仕事がいい、という人が多いのでは。もちろん私も専業主婦でしたから、その気持ちは分かります。ただ、お金を嫁ぐということに無関心になりがちで、それをいいことに悪質な語学学校が女性教師を低賃金で雇うなど、トラブルの元になることもあります」 ―日本人は一般に、外国人との付き合いがヘタだといわれますが。 「日本は縦社会だからでしょうか、すぐに外国人を自分の上か下かに分類したがるんですね。欧米人にはへりくだり、アジアの人にはいばる、といった旦谷です。どこの国の人とでも平等に付き合うという姿勢を持ちたいものです。日本語教師になると、そういった偏見はなくなっていきます。技術だけではなく、人間性を兼ね備えた日本語教師が増えていけば、と思います」 (聞き手は福士千恵子記者) 1988年2月9日 読売新聞 |