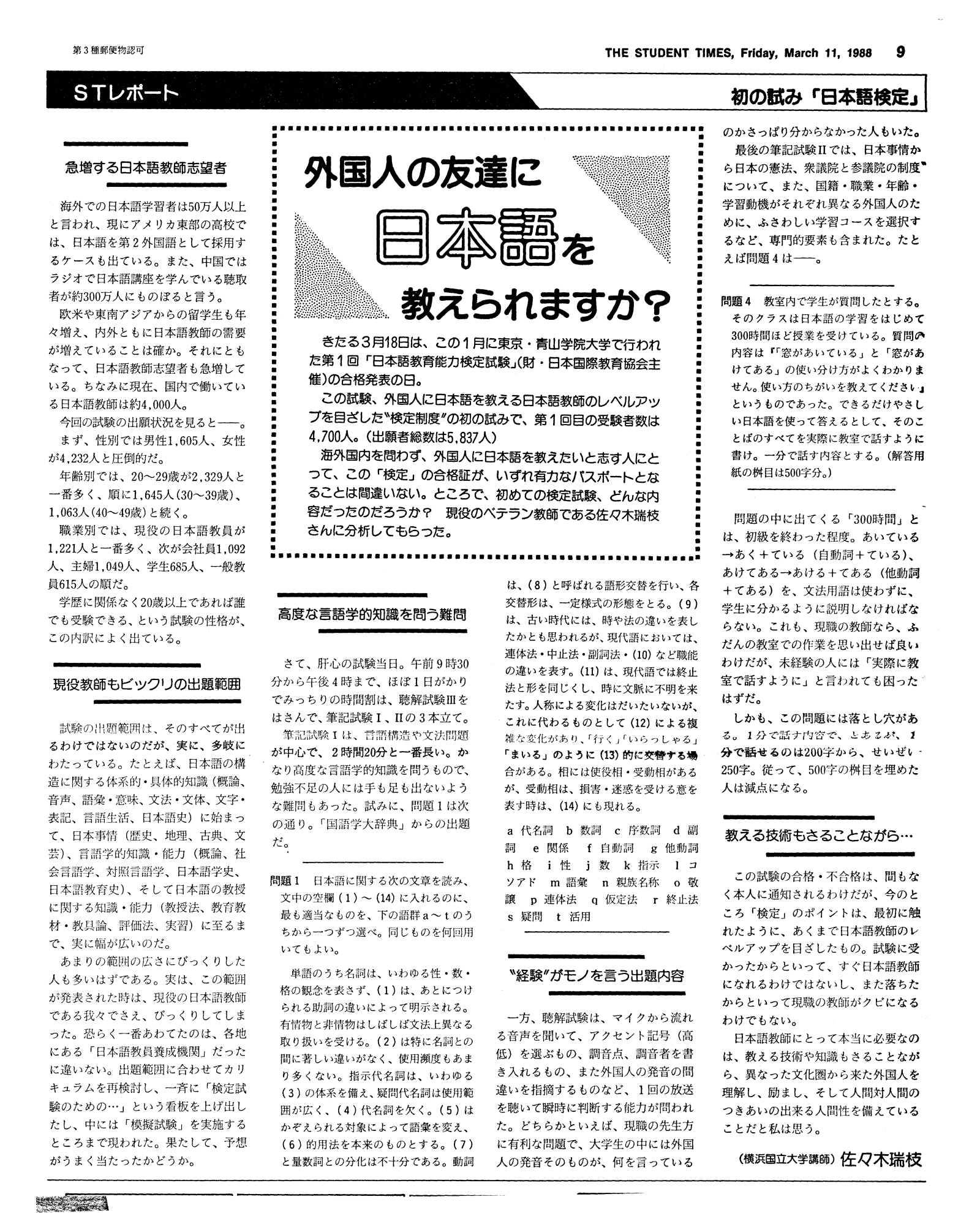
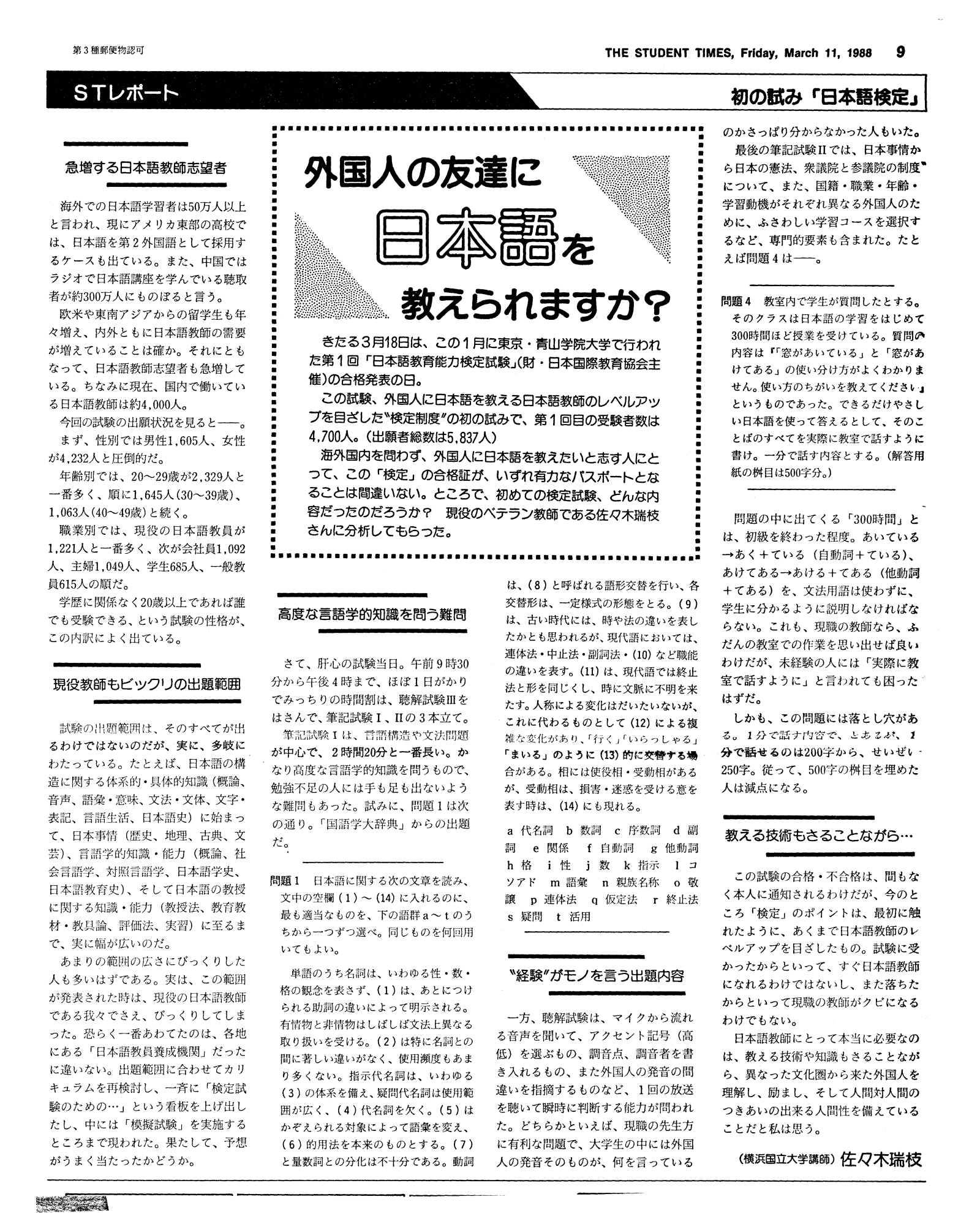
| THE STUDENT TIMES, Friday, March 11, 1988 ST レポート 初の試み「日本語検定」 外国人の友達に日本語を教えられますか? きたる3月18日は、この1月に東京・青山学院大学で行われた第1回「日本語教育能力検定試験J(財・日本国際教育協会主催)の合格発表の日。 この試験、外国人に日本語を教える日本語教師のレベルアップを目ざした"検定制度"の初の試みで、第1回目の受験者数は4,700人。(出願者総数は5,837人) 海外国内を問わず、外国人に日本語を教えたいと志す人にとって、この「検定」の合格証が、いずれ有力なパスポートとなることは間違いない。ところで、初めての検定試験、どんな内容だったのだろうか?現役のベテラン教師である佐々木瑞枝さんに分析してもらった。 急増する日本語教師志望者 海外での日本語学習者は50万人以上と言われ、現にアメリカ東部の高校では、日本語を第2外国語として採用するケースも出ている。また、中国ではラジオで日本語講座を学んでいる聴取者が約300万人にものぼると言う。 欧米や東南アジアからの留学生も年々増え、内外ともに日本語教師の需要が増えていることは確か。それにともなって、日本語教師志望者も急増している。ちなみに現在、国内で働いている日本語教師は約4,000人。 今回の試験の出願状況を見ると―。 まず、性別では男性1,605人、女性が4,232人と圧倒的だ。年齢別では、20~29歳が2,329人と一番多く、順に1,645人(30~39歳)、1,063人(40~49歳)と続く。 職業別では、現役の日本語教員が1,221人と一番多く、次が会社員1,092人、主婦1,049人、学生685人、一般教員615人の順だ。 学歴に関係なく20歳以上であれば誰でも受験できる、という試験の性格が、この内訳によく出ている。 現役教師もビックリの出題範囲 試験の出題範囲は、そのすべてが出るわけではないのだが、実に、多岐にわたっている。たとえば、日本語の構造に関する体系的・具体的知識(概論、音声、語彙・意味、文法・文体、文字・表記、言語生活、日本語史)に始まって、日本事情(歴史、地理、古典、文芸)、言語学的知識・能力(概論、社会言語学、対照言語学、日本語学史、日本語教育史)、そして日本語の教授に関する知識・能力(教授法、教育教材・教具論、評価法、実習)に至るまで、実に幅が広いのだ。 あまりの範囲の広さにびっくりした人も多いはずである。実は、この範囲が発表された時は、現役の日本語教師である我々でさえ、びっくりしてしまった。恐らく一番あわてたのは、各地にある「日本語教員養成機関」だったに違いない。出題範囲に合わせてカリキュラムを再検討し、一斉に「検定試験のための…」という看板を上げ出したし、中には「模擬試験」を実施するところまで現われた。果たして、予想がうまく当たったかどうか。 高度な言語学的知識を問う難問 さて、肝心の試験当日。午前9時30分から午後4時まで、ほぼ1日がかりでみっちりの時間割は、聴解試験Ⅲをはさんで、筆記試験I、Ⅱの3本立て。 筆記試験1は、言語構造や文法問題が中心で、2時間20分と一番長い。かなり高度な言語学的知識を問うもので、勉強不足の人には手も足も出ないような難問もあった。試みに、問題1は次の通り。「国語学大辞典」からの出題だ。 問題1 日本語に関する次の文章を読み、文中の空欄(1)~(14)に入れるのに、最も適当なものを、下の語群a~tのうちから一つずつ選べ。同じものを何回用いてもよい。 単語のうち名詞は、いわゆる性・数・格の観念を表さず、(1)は、あとにつけられる助詞の違いによって明示される。有情物と非情物はしばしば文法上異なる取り扱いを受ける。(2)は特に名詞との間に著しい違いがなく、使用瀕度もあまり多くない。指示代名詞は、いわゆる(3)の体系を備え、疑問代名詞は使用範囲が広く、(4)代名詞を欠く。(5)はかぞえられる対象によって語彙を変え、(6)的用法を本来のものとする。(7)と量数詞との分化は不十分である。動詞は、(8)と呼ばれる語形交替を行い、各交替形は、一定様式の形態をとる。(9)は、古い時代には、時や法の違いを表したかとも思われるが、現代語においては、連体法・中止法・副詞法・(10)など職能の違いを表す。(11)は、現代語では終止法と形を同じくし、時に文脈に不明を来たす。人称による変化はだいたいないが、これに代わるものとして(12)による複雑な変化があり、「行く」「いらっしゃる」「まいる」のように(13)的に交替する場合がある。相には使役相・受動相があるが、受動相は、損害・迷惑を受ける意を表す時は、(14)にも現れる。 a 代名詞 b 数詞 c 序数詞 d 副詞 e 関係 f 自動詞 g 他動詞 h 格 i 性 j 数 k 指示 l コソアド m 語彙 n 親族名称 o 敬譲 p 連体法 q 仮定法 r 終止法 s 疑問t 活用 "経験"がモノを言う出題内容 一方、聴解試験は、マイクから流れる音声を聞いて、アクセント記号(高低)を選ぶもの、調音点、調音者を書き入れるもの、また外国人の発音の間違いを指摘するものなど、1回の放送を聴いて瞬時に判断する能力が問われた。どちらかといえば、現職の先生方に有利な問題で、大学生の中には外国人の発音そのものが、何を言っているのかさっぱり分からなかった人もいた。 最後の筆記試験Ⅱでは、日本事情から日本の憲法、衆議院と参議院の制度鶏について、また、国籍・職業。年齢・学習動機がそれぞれ異なる外国人のために、ふさわしい学習コースを選択するなど、専門的要素も含まれた。たとえば問題4は―。 問題4 教室内で学生が質問したとする。 そのクラスは日本語の学習をはじめて300時間ほど授業を受けている。質問の内容は『「窓があいている」と「窓があけてある」の使い分け方がよくわかりません。使い方のちがいを教えてください』というものであった。できるだけやさしい日本語を使って答えるとして、そのことばのすべてを実際に教室で話すように書け。一分で話す内容とする。(解答用紙の桝目は500字分。) 問題の中に出てくる「300時間」とは、初級を終わった程度。あいている→あく+ている(自動詞+ている)、あけてある→あける+てある(他動詞+てある)を、文法用語は使わずに、学生に分かるように説明しなければならない。これも、現職の教師なら、ふだんの教室での作業を思い出せば良いわけだが、未経験の人には「実際に教室で話すように」と言われても困ったはずだ。 しかも、この問題には落とし穴がある。1分で話す内容で、とあるが、1分で話せるのは200字から、せいぜい250字。従って、500字の桝目を埋めた人は減点になる。 教える技術もさることながら… この試験の合格・不合格は、間もなく本人に通知されるわけだが、今のところ「検定」のポイントは、最初に触れたように、あくまで日本語教師のレベルアップを目ざしたもの。試験に受かったからといって、すぐ日本語教師になれるわけではないし、また落ちたからといって現職の教師がクビになるわけでもない。 日本語教師にとって本当に必要なのは、教える技術や知識もさることながら、異なった文化圏から来た外国人を理解し、励まし、そして人間対人間のつきあいの出来る人間性を備えていることだと私は思う。 (横浜国立大学講師)佐々木瑞枝 |