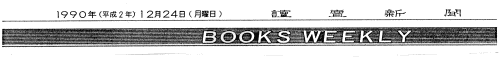
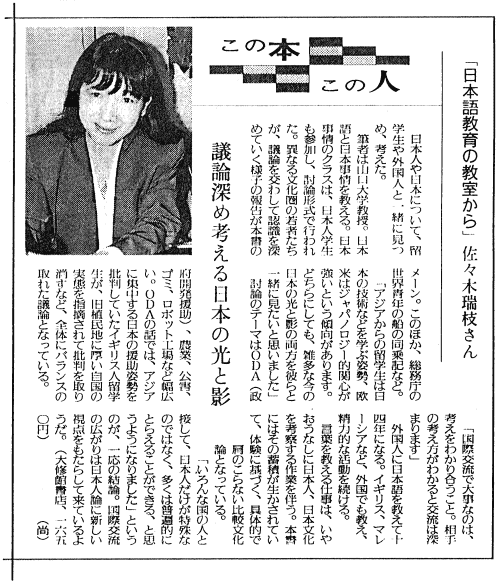
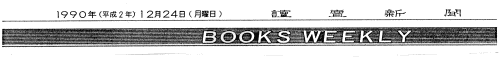
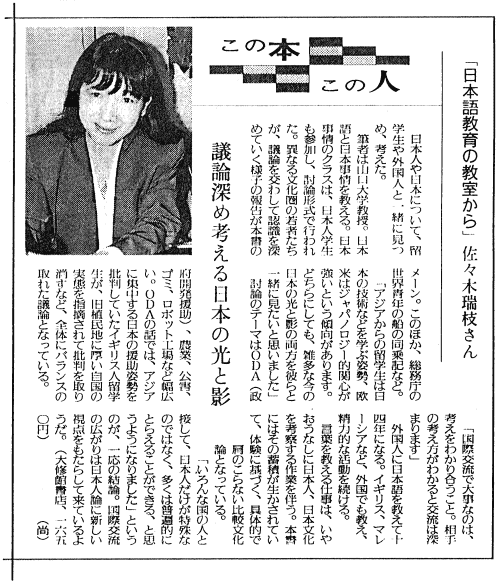
|
「日本語教育の教室から」 佐々木瑞枝さん
議論深め考える日本の光と影 日本人や日本について、留学生や外国人と一緒に見つめ、考えた。 筆者は山口大学教授。日本語と日本事情を教える。日本事情のクラスは、日本人学生も参加し、討論形式で行われた。異なる文化圏の若者たちが、議論を交わして認識を深めていく様子の報告が本書のメーン。このほか、総務庁の世界青年の船の同乗記など。 「アジアからの留学生は日本の技術などを学ぶ姿勢、欧米はジャパノロジー的関心が強いという傾向があります。どちらにしても、雑多な今の日本の光と影の両方を彼らと一緒に見たいと思いました」 討論のテーマはODA(政府開発援助)、農業、公害、ゴミ、ロボット工場など幅広い。ODAの話では、アジアに集中する日本の援助姿勢を批判していたイ ギリス人留学性が、旧植民地に厚い自国の実態を指摘されて批判を取り消すなど、全体にバランスの取れた議論となっている。 「国際交流で大事なのは、考えをわかり合うこと。相手の考え方がわかると交流は深まります」 外国人に日本語を教えて十四年になる。イギリス、マレーシアなど、外国でも教え、精力的な活動を続ける。 言葉を教える仕事は、いやおうなしに日本人、日本文化を考察する作業を伴う。本書にはその蓄積が生かされていて、体験に基づく、具体的で肩のこらない比較文化論となっている。 「いろんな国の人と接して、日本人だけが特殊なのではなく、多くは普遍的にとらえることができる、と思うようになりました」というのが、一応の総論。国際交流の広がりは日本人諭に新しい視点をもたらして来ているようだ。(大修館書店、二六五0円) (尚) |