
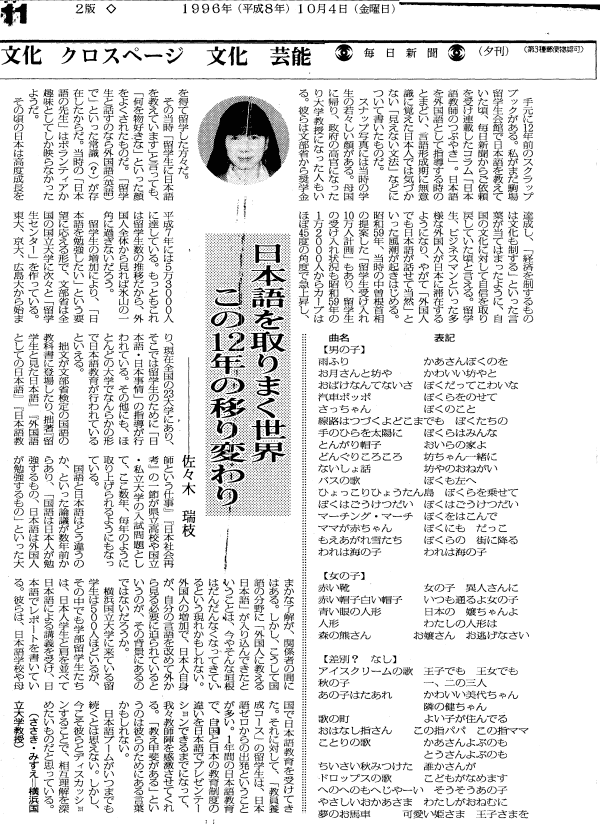

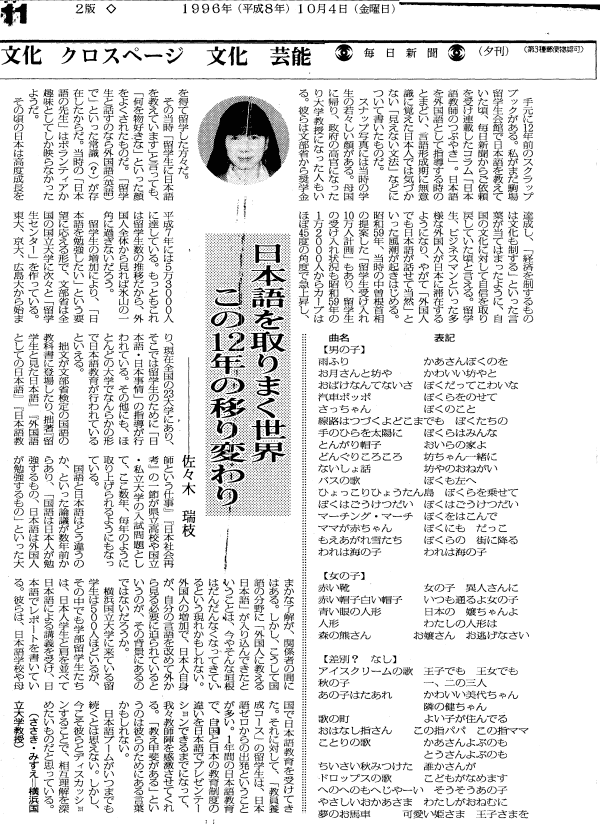
|
どうして「ぼく」なの?!
童謡・唱歌…留学生の疑問 指摘された”女性差別” 日本語ブームが、内外で続いている。留学生問題の関係者が「10年前ならとても考えられないような」というほどの層と厚みを持ったものになっているとい う。こうした中でこの夏から話題になっているのが、「どうして『ぼく』なの?」というドイツ人女性留学生の問いかけから始まった日本の童謡や唱歌の〝女性 差別″問題。日本人が全く気づかなかった指摘だ。合わせて横浜国立大学留学生センター教授の佐々木瑞枝さんに日本語ブームの背景を執筆してもらった。 【桐原 良光】
佐々木瑞枝さんが、留学生に日本語を教える難しさ、留学生から教えられたことなどをNHKラジオ放送で話した中に「どうして『ぼく』なの?」があった。 『汽車ポッポ』(留原薫作詞)に乗って行くのは、どうして「ぼくら」だけなのですか? 『手のひらに太陽を』 (やなせたかし作詞)受けて生きているのは 「ぼくら」だけじゃないでしょう? という留学生の疑問を話した。 早朝の放送だったにもかかわらず「目からウロコが落ちる思いをした」と驚くほどの反響があった。お年寄りが多かったが、長い巻紙に歌詞を写したり、歌集 から20枚ものコピーを同封してくれた人もいた。「ぼくらは3組」で始まる『それ行け3組』では「この学校は男子校?」などという皮肉を込めたコメントも あった。 「彼女は歌への疑問から始まって、これは日本の社会を見るのにいいテーマだと言うのです。私が、たまたま子供の代表としての『ぼく』で、日本語は女言葉 と男言葉の差の大きな言語であることも説明し、『差別とは違うと思う』といっても聞かないのです」と佐々木さん。 佐々木さん白身の大学院マスター論文が「男言葉、女言葉」であったが、この指摘には驚いた。「私はウーマン・リブではないんですけれど、女性学の立場か らいえば差別かもしれませんね。彼女は、はっきりと『差別です』といってました。日本は、女性が働きに出ても家庭に入ると辞めてしまい、ひと区切りつくと またパートに出たりする。辞めること自体がおかしい。 これは日本に女性差別があるからというのです」 問題は日本社会の構造にまで広がってしまったが、童謡・唱歌に戻すと、ザッと調べただけでも別表のように確かに「ぼく」や「坊や」が多い。 「さっちゃん」や「マーチング・マーチ」で「ぼく」と書いた作家の阪田寛夫さんは「この歌の主人公は、ぼく自身の分身でもあるので、ぼく・ぼくらになり ます。『わたし』で書いたこともあるのですが、少女を主体にして痛切な思いを歌うことが私には難しくて、一人称抜きの歌が多くなりました」と語る。阪田さ んは、これまでの童謡詩人がほぼ男性であったことを指摘し、「最近の新人は全部女性といってもいいぐらいですから、ぼく・わたしの比率は今に逆転します よ」と、このドイツ人留学生には、うれしい予想。 しかし「ひょっこりひょうたん島」で「だけどぼくらはくじけない」と書いた作家の井上ひさしさんは「日本語の特性などから『ぼく』はやむをえない」と次の ように説明する。 ①歌にする場合の基本は5語。日本語には助詞が付くから『ぼく』なら『ぼくと空』などのようにもうひとつ言葉を入れられるが、『わたし』に助詞を付ける ともう言葉を入れられないし、表現がダラダラしてしまう②『わたし』だと文語的表現に近くなり、口語的表現である歌にはあまり合わない③『ぼく』は社会人 になっても使っていると直されるぐらい幼児語の印象が強く、男の子には使いやすい。 さて、あなたは「ぼく」派、それとも「わたし」派?
日本語を取りまく世界
この12年の移り変わり 手元に12年前のスクラップブックがある。私がまだ駒場留学生会館で日本語を教えていた頃、毎日新聞からご依頼を受け連載したコラム「日本語教師のつ ぶやき」。日本語を外国語として指導する時のとまどい、言語形成期に無意識に覚えた日本人では気づかない「見えない文法」などについて書いたものだ。 スナップ写真には当時の学生の若々しい顔がある。母国に帰り、政府の高官になったり大学教授になった人もいる。彼らは文部省から奨学金を得て留学した方 々だ。 その当時「留学生に日本語を教えています」と言っても、「何を物好きな」といった顔をよくされたものだ。「留学生と話すのなら外国語(英語)で」といっ た常識(?)が存在したからだ。当時の「日本語の先生」はボランティアか趣味としてしか映らなかったようだ。 その頃の日本は高度成長を達成し、「経済を制するものは文化も制する」といった言葉が当てはまったように、自国の文化に対して自信を取り戻していた頃と 言える。留学生、ビジネスマンといった多様な外国人が日本に滞在するようになり、やがて「外国人でも日本語が話せて当然」といった風潮が起きはじめる。昭 和59年、当時の中曽根首相の提案した「留学生受け入れ10万人計画」もあり、留学生の受け入れ状況も昭和59年の1万2000人からカーブはほぼ45度 の角度で急上昇し、平成7年には5万3000人に達している。もっともこれは留学生数の推移だから、外国人全体から見れば氷山の一角に過ぎないだろう。 留学生の増加により、「日本語を勉強したい」という要望に応える形で、文部省は全国の国立大学に次々と「留学生センター」を作っている。東大、京大、広 島大から始まり、現在全国の23大学にあり、そこでは留学生のために「日本語・日本事情」の指導が行われている。その他にも、ほとんどの大学でなんらかの 形で日本語教育が行われているといえる。 拙文が文部省検定の国語の教科書に登場したり、拙著『留学生と見た目本譜』『外国語としての日本語』『日本語教師という仕事』『日本社会再考』の一節が 県立高校や国立・私立大学の入試問題として、ここ数年、毎年のように取り上げられるようにもなっている。 国語と日本語はどう違うのか、といった論議が数年前からあり、「国語は日本人が勉強するもの、日本語は外国人が勉強するもの」といった大まかな了解が、 関係者の間にはある。しかし、こうして国語の分野に「外国人に教える日本語」が入り込んできたということは、今やそんな垣根はだんだんなくなってきている という現れかもしれない。外国人の増加で、日本人自身が、自分の言語を改めて外から見る必要に迫られているというのが、その背景にあるのではないだろう か。 横浜国立大学に来ている留学生は500人ほどいるが、その中でも学部留学生たちは、日本人学生と肩を並べて日本語による講義を受け、日本語でレポートを 書いている。彼らは、日本語学校や母国で日本語教育を受けてきた。それに対して、「教員養成コース」の留学生は、日本語ゼロからの出発ということが多い。 1年間の日本語教育で、自国と日本の教育制度の違いを日本語でプレゼンテーションできるまでになって、我々教師陣を感激させてくれる。「教え甲斐がある」 というのは彼らのためにある言葉かもしれない。 日本語ブームがいつまでも続くとは思えない。しかし、今こそ彼らとディスカッションすることで、相互理解を深めたいものだと思っている。 (ささき・みずえ=横浜国立大学教授)
|