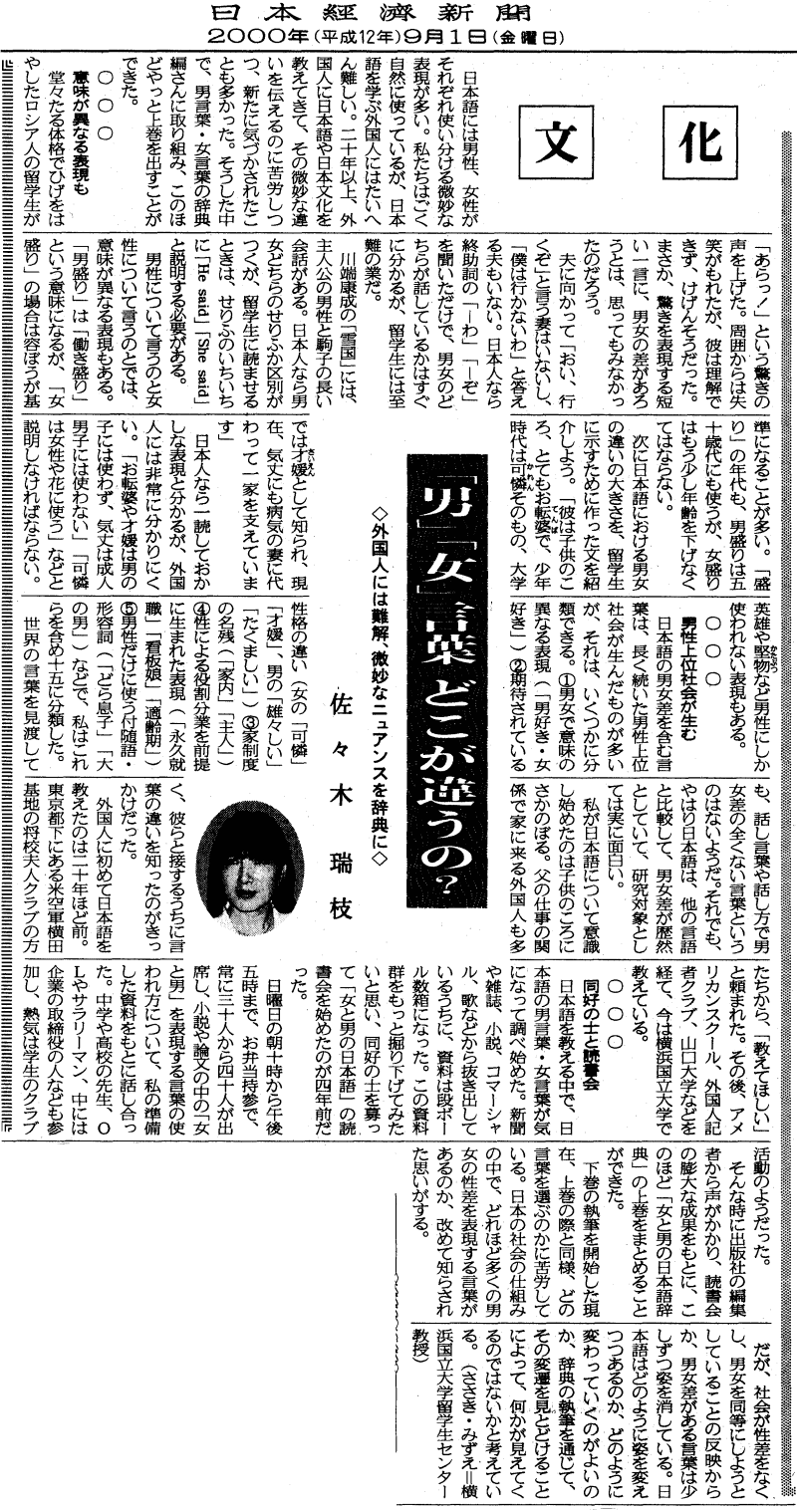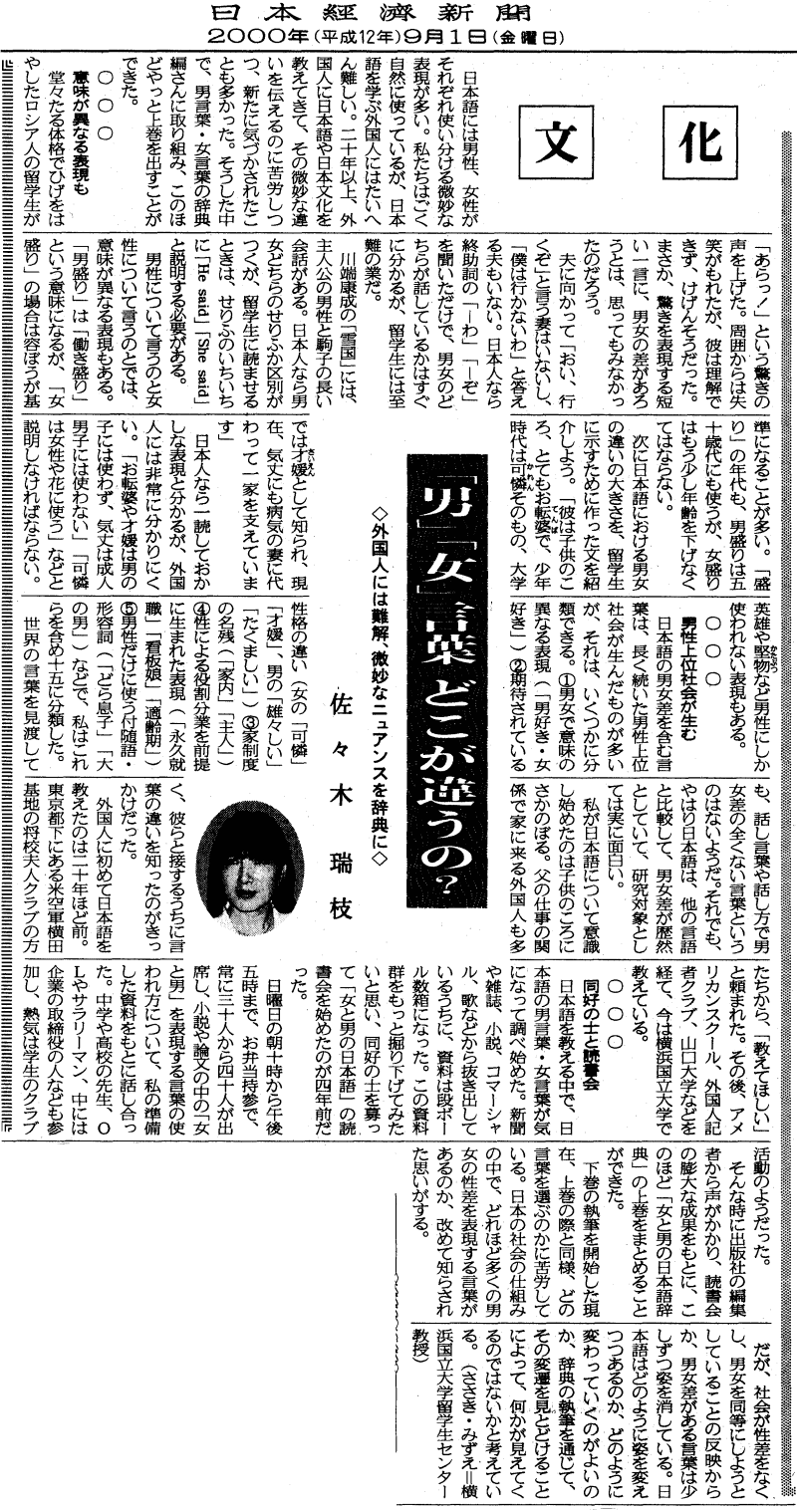
|
「男」「女」言葉どこが違うの? ◇外国人には難解、微妙なニュアンスを辞典に◇ 佐々木瑞枝 日本籍には男性、女性がそれぞれ使い分ける微妙な表現が多い。私たちはごく自然に使っているが、日本語を学ぶ外国人にはたいへん難しい。二十年以上、外国人に日本語や日本文化を教えてきて、その微妙な速いを伝えるのに苦労しつつ、新たに気づかされたことも多かった。そうした中で、男言葉・女言葉の辞典編さんに取り組み、このほどやっと上巻を出すことができた。 ○ ○ ○ 意味が異なる表現も 堂々たる体格でひげをはやしたロシア人の留学生が「あらっ!」という驚きの声を上げた。周囲からは失笑がもれたが、彼は理解できず、けげんそうだった。 まさか、驚きを表現する短い一言に、男女の差があろ うとは、思ってもみなかったのだろう。 夫に向かって「おい、行くぞ」と言う妻はいないし、「僕は行かないわ」と答える夫もいない。日本人なら終助詞の「-わ」 「-ぞ」を聞いただけで、男女のどちらが話しているかはすぐに分かるが、留学生には至難の業だ。 川端康成の「雪国」には、主人公の男性と駒子の長い会話がある。日本人なら男女どちらのせりふか区別がつくが、留学生に読ませるときは、せりふのいちいちに「He said」 「She said」と説明する必要がある。 男性について言うのと女性について言うのとでは、意味が異なる表現もある。 「男盛り」は「働き盛り」という意味になるが、「女盛り」の場合は容ぼうが基準になることが多い。「盛り」の年代も、男盛りは五十歳代にも使うが、女盛りはもう少し年齢を下げなくてはならない。 次に日本語における男女の違いの大きさを、留学生に示すために作った文を紹介しよう。「彼は子供のころ、とても説教で、少年時代は可憐そのもの、大学では才媛として知られ、現在、気丈にも病気の妻に代わって一家を支えています」 日本人なら一読しておかしな表現と分かるが、外国人には非常に分かりにくい。「お転婆や才媛は男の子には使わず、気丈は成人男子には使わない」「可憐は女性や花に使う」などと説明しなければならない。英雄や堅物など男性にしか使われない表現もある。 ○ ○ ○ 男性上位社会が生む 日本語の男女差を含む言葉は、長く続いた男性上位社会が生んだものが多いが、それは、いくつかに分類できる。①男女で意味の異なる表現(「男好き・女好き」)②期待されている性格の速い(女の「可憐」「才媛」、男の「雄々しい」「たくましい」)③家制度の名残(「家内」「主人」)④性による役割分業を前提に生まれた表現(「永久就職」「看板娘」「適齢期」)⑤男性だけに使う付随語・形容詞(「どら息子」「大の男」)などで、私はこれらを含め十五に分類した。 世界の言葉を見渡しても、話し言葉や話し方で男女差の全くない言葉というのはないようだ。それでも、やはり日本語は、他の言語と比較して、男女差が歴然としていて、研究対象としては実に面白い。 私が日本語について意識し始めたのは子供のころにさかのぼる。父の仕事の関係で家に来る外国人も多く、彼らと接するうちに言葉の違いを知ったのがきっかけだった。 外国人に初めて日本語を教えたのは二十年ほど前。東京都下にある米空軍横田基地の将校夫人クラブの方たちから、教えてほしい」と頼まれた。その後、アメリカンスクール、外国人記者クラブ、山口大学など券経て、今は横浜国立大学で教えている。 ○ ○ ○ 同好の士と読書会 日本語を教える中で、日本語の男言葉・女言葉が気になって調べ始めた。新闇や雑誌、小説、コマーシャル、歌などから抜き出しているうちに、資料は段ボール数箱になった。この資料群をもっと掘り下げてみたいと思い、同好の士を募って「女と男の日本語」の読書会を始めたのが四年前だった。 日曜日の朝十時から午後五時まで、お弁当持参で、常に三十人から四十人が出席し、小説や論文の中の「女と男」を表現する言葉の使われ方について、私の準備した資料をもとに話し合った。中学や高校の先生、0Lやサラリーマン、中には企業の取締役の人なども参加し、熱気は学生のクラブ活動のようだった。 そんな時に出版社の編集着から声がかかり、読書会の膨大な成果をもとに、このほど「女と男の日本語辞典」の上巻をまとめることができた。 下巻の執筆を開始した現在、上巻の際と同様、どの言葉を選ぶのかに苦労している。日本の社会の仕組みの中で、どれほど多くの男女の性差を表現する言葉があるのか、改めて知らされた思いがする。 だが、社会が性差をなくし、男女を同等にしようとしていることの反映からか、男女差がある言葉は少しずつ姿を消している。日本語はどのように姿を変えつつあるのか、どのように変わっていくのがよいのか、辞典の執筆を通じて、その変遷を見とどけることによって、何かが見えてくるのではないかと考えている。 (ささき・みずえ=横浜国立大学留学生センター教授) 日本経済新聞 2000(平成12年)9月1日(金曜日) |