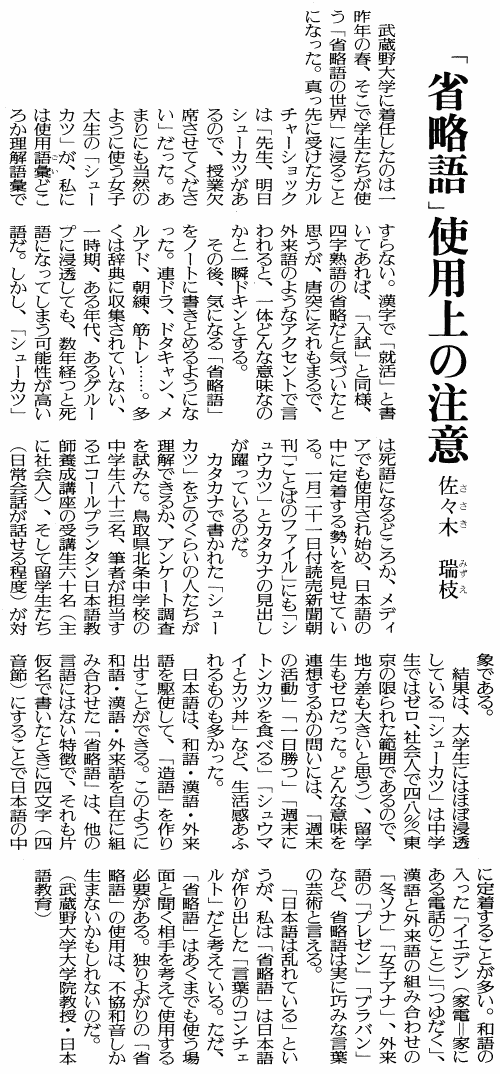
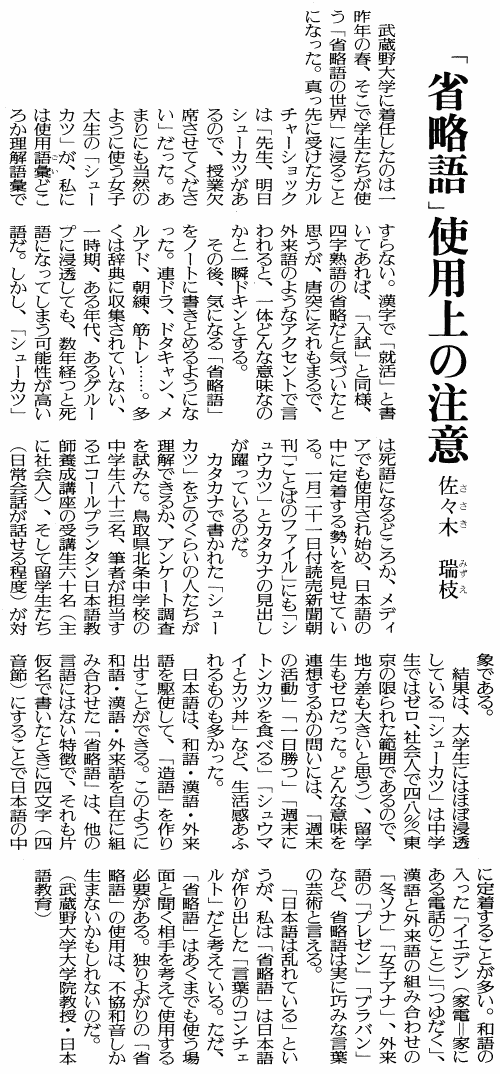
|
「省略語」使用上の注意
佐々木瑞枝 武蔵野大学に着任したのは一昨年の春、そこで学生たちが使う「省略語の世界」に浸る ことになった。真っ先に受けたカルチャーショックは「先生、明日シェーカツがあるので、授業欠席させてください」だった。あまりにも当然のように使う女子 大生の「シューカツ」が、私には使用語彙どころか理解語彙ですらない。漢字で「就活」と書いてあれば、「入試」と同様、四字熟語の省略だと気づいたと思う が、唐突にそれもまるで、外来語のようなアクセントで言われると」一体どんな意味なのかと一瞬ドキンとする。 その後、気になる「省略語」をノートに書きとめるようになった。連ドラ、ドタキャン、メルアド、朝練、筋トレ……。多くは辞典に収集されていない、一時 期、ある年代、あるグループに浸透しても、数年経つと死語になってしまう可能性が高い語だ。しかし、「シューカツ」は死語になるどころか、メディアでも使 用され始め、日本語の中に定着する勢いを見せている。一月二十一日付読売新聞朝刊「ことばのファイル」にも「シュウカツ」とカタカナの見出しが躍っている のだ。 カタカナで書かれた「シューカツ」をどのくらいの人たちが理解できるか、アンケート調査を試みた。鳥取県北条中学校の中学生八十三名、筆者が担当するエ コールプランタン日本語教師養成講座の受講生六十名(主に社会人)、そして留学生たち(日常会話が話せる程度)が対象である。 結果は、大学生にはほぼ浸透している「シューカツ」は中学生ではゼロ、社会人で四八%(東京の限られた範囲であるので、地方差も大きいと思う)、留学生 もゼロだった。どんな意味を連想するかの問いには、「週末の活動」 「一日勝つ」 「週末にトンカツを食べる」 「シュウマイとカツ井」など、生活感あふ れるものも多かった。 日本語は、和語・漢語・外来語を駆使して、「造語」を作り出すことができる。このように和語・漢語・外来語を自在に組み合わせた「省略語」は、他の言語 にはない特徴で、それも片仮名で書いたときに四文字(四書節)にすることで日本語の中に定着することが多い。和語の入った「イエデン(家電=家にある電話 のこと)」「つゆだく」、漢語と外来語の組み合わせの「冬ソナ」 「女子アナ」、外来語の「プレゼン」 「ブラバン」など、省略語は実に巧みな言葉の芸術 と言える。 「日本語は乱れている」というが、私は「省略語」は日本語が作り出した「言葉のコンチェルト」だと考えている。ただ、「省略語」はあくまでも使う場面と 聞く相手を考えて使用する必要がある。独りよがりの「省略語」の使用は、不協和音しか生まないかもしれないのだ。 (武蔵野大学大学院教授・日本語教育)
|