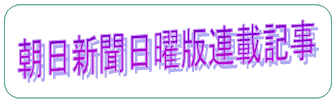
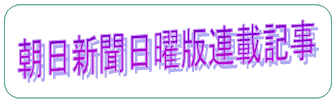
目次
1997年6月15日 日曜日 ポパポパ四月に来日した留学生たちも、日本の生活にすっかり慣れて、楽しそうに授業に顔を見せる。日本特有のジメジメした梅雨の季節さえ、彼らは楽しんでいるかのようだ。「先生、今日も雨ですね。でも、日本の雨はタイの雨とはぜんぜん違いますね」と、タイからの留学生プラユーン君。「タイの雨はサーサー、強い雨。でも、日本の雨は……?」。表現に詰まったのか困ったような顔をして、私を見つめる。 「こういう雨はねー」。私は外を指しながら「シトシト」と教える。 「メキシコではチビチビです」とホルン君。スペイン語にも、しめやかに降る雨の音を指す擬音語が存在するようだ。 タイで雨といえば、スコールを意味する。日本語のザーザーに当たる「サーサー」はあるが、シトシトと一日中降る雨の擬音語はない。強いてあげるなら「ポパポパ」で、これは日本語のポツポツに似ている。スコールになる前に降りだす雨の音だ。 擬音語は、外界の音と直接的なつながりがある。「シトシト」はやはり日本でしか味わえない事柄の一つだろう。 「先生、じやあ、あの音は?」。いたずらっ子のような笑顔で、ハンガリーの留学生が聞く。耳を澄ますと、空のはるかかなたで、雷の音がする。埼玉の上空あたりで、今ごろ雷様が大暴れしているのかもしれない。 「あれはね、ゴロゴロ」 思いっきり低い声で答えると、留学生たちもまねして、「ゴロゴロ、ゴロゴロ」。雷は世界共通の自然現象だから、かえって理解しやすいのだろう。 「でも、私たちの言葉にはこういう表現はぜんぜんありません」と、フランスやインドネシアからの留学生たち。擬音語・擬態語には二語の反復が多い。そのほかにも特有のパターンがある。どんな風に教えるか、それが悩みだ。 |
1997年6月22日 日曜日 降りる時に 大学会館の前で、インドからの留学生アニルさんが、彼のチューター(相談相手)の木村君と話している。 |
1997年6月29日 日曜日 約束を解約する 初夏の日差しの中を三人の若者たちが留学生センターを訪れた。留学生の話し相手にお招きしたのだ。 |
1997年7月6日 日曜日 狭いもので いよいよ夏休みが近づいてきた。
留学生にホームステイを体験させたいと、日本人家庭の方々とお見合いの機会を作った。たった数日の滞在でも、相性によって留学生の日本人観がまったく変
わるからだ。シングルの女性は案外スンナリと決まる。ところが、男性で奥さん、子供連れとなるとなかなか受け入れてくれる人がいない。 |
1997年7月13日 日曜日 ただの日本語教師 都内のホテルのパーティー会場は、華やかな雰囲気にあふれ、秋篠宮妃の紀子様がにこやかに談笑されている。今日はある新聞社の児童出版文化賞贈呈式で、拙著「日本語ってどんな言葉?」(筑摩書房)も受賞することになったのだった。 |
1997年7月20日 日曜日 「来っていますか」 留学生たちを、我が家の食事に招いた。今日は総勢十一人。何をどのくらい作ったらよいのか見当がつかない。 |
1997年7月27日 日曜日 拝啓 森有礼様 神奈川県の葉山町に総合研究大学院大学がある。国立大学としては異例の、学部を持たない、大学院だけの大学である。 |
1997年8月3日 日曜日 異文化間の対話 日本語の上級レベルに達した留学生を対象にした「日本事情」という科目がある。
十年ほど前、山口大学で初めてこの科目を担当することになった時は、何を教えるのか、どんな風に教えるのか、テキストはあるのか、全く分からず当惑した。 |