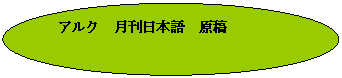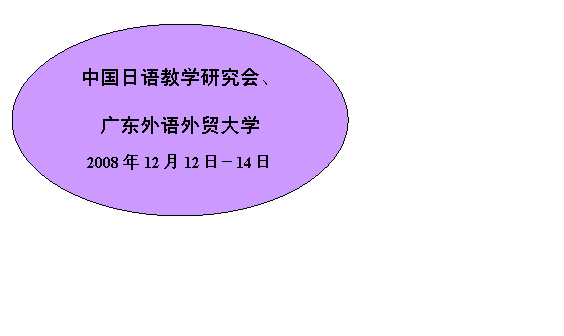

開会挨拶 修剛 天津外国語学院長

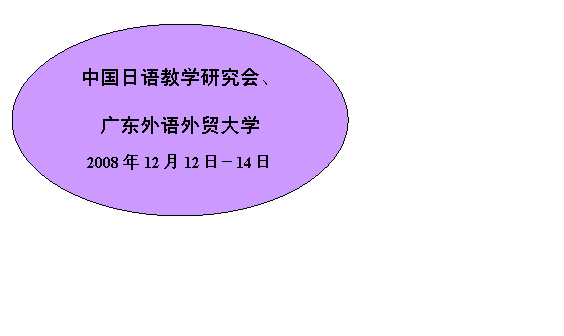

| 13:30-16:24主持人:丁国旗(广东外语外贸大学东语学院日语系主任,教授) | 13:40-14:00 | 报告人:石塚 晴通(北海道大学名誉教授) 题目:十七条の憲法―日本人の常識・道徳― |
| 14:00-14:20 | 报告人:顾也力(广东外语外贸大学副校长)题目:刍议高校专业日语教材编写之实施纲要 | |
| 14:20-14:40 | 报告人:韦立新(广东外语外贸大学日本研究中心主任教授)题目:日本神道の成立をめぐる研究について | |
| 14:40-15:00 | 报告人: >佐々木瑞枝(武蔵野大学大学院教授)题目:「自然な日本語指導の工夫」-形式名詞を例に | |
| 15:20-15:40 | 报告人:曹大峰(北京日本学研究中心副主任,教授)题目:中国人学習者向けの日本語教育文法の再構築-専攻用基礎教材の文法シラバス研究 | |
| 15:40-16:00 | 报告人:揭侠(南京国际关系学院教授)题目:日语的同格、倒装及移就辞格 | |
| 16:00-16:08 | 报告人:北京大学出版社领导 | |
| 16:08-16:16 | 报告人:大连理工大学出版社领导 | |
| 16:16-16:24 | 报告人:华东师范大学出版社领导 | |
| 茶歇(16:24-16:40)(第六教学大楼一楼) | ||
| 闭幕式(16:40-18:00,第六教学大楼一楼演讲厅) | ||