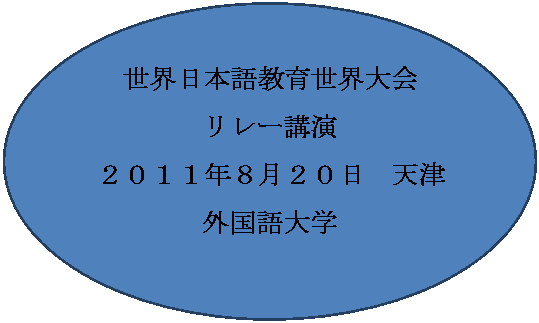
暑い天津の8月、熱い思いを胸に秘め、2000名もの日本語教育関係者が一堂に会した。
| ■リレー講演 |
| コミュンミケーション重視の「日本事情教育」をどう展開するか? アメリカ:牧野成一(プリンストン大学) 中国:修剛(天津外国語大学) 日本:佐々木瑞枝(武蔵野大学) 韓国:李 康民(漢陽大学) ハンガリー:ジュリット ヒダシ(ハンガリー商科大学) 王鉄橋(洛陽外国語大学) 今後、日本事情教育は知識重視からコミュニケーション重視の教育へと移行させるべきである。各国でどう展開したら良いのだろう。各国6人の代表によるリレー講演。 |

リレー講演風景
リレー講演打ち合わせ(ルネッサンスホテルで)
天津 ルネッサンスホテル前の風景
中川文部科学大臣を囲んで

久しぶりに水谷修先生とお話ししました。
手前は椎名和夫先生

レストランのインテリア
8月19日夜の宴会で
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グローバル・ボーダレスな多文化共生社会の中にあって、外国語として日本語を学ぶ理由として「日本や日本の文化に興味があるから」
を理由の筆頭にあげる人が多い。コミュニケーション能力を育てるには、彼らの興味のあるところから「日本について学ぶ」ことが、
言語能力や社会言語学的能力、ストラテジー能力を育てることとともに重要なのではないだろうか。それはとりもなおさず、
日本語を学ぶことで相手の文化を尊重し、お互いを認め合い、高めあう「ともに生きる社会」を創造することにつながるのではないかと思う。
しかし、世界における日本語教育の状況をみれば、最近確かに多くの日本語教材が開発されてきたが、「日本の文化」は日本語教材の中に断片的に
「日本事情的要素」として入ることはあっても、「日本事情」を俯瞰的にとらえ、
異文化コミュニケーション能力を育成するための素材を盛り込んだ教科書は数えるほどしかなく、
授業の中でも付随的に扱われている例が大半である。
そのような課題に直面して、中国の高等教育出版では「新日本事情」の教科書の企画が行なわれ、
北京の10大学の日本事情担当者でディスカッションが行なわれた。その結果を踏まえ大学日本語科2年生用の教材として執筆が進められてきた。
「新日本事情」には多文化理解と共生能力の育成を目標に、内容重視とタスク中心の学習活動を盛り込み、
30課からなる教科書が日本人の著者と中国人のコラム担当者で執筆が進められている。
このリレー講演では、「多文化共生能力を育成する日本事情の教科書はなぜ必要なのか、世界を視野においた日本事情教材はどうあるべきか、世界ではどのような日本事情教育が展開されているのか」などの課題をめぐって、中国・日本・アメリカ・ヨーロッパ・韓国」の講演者により、「日本事情教育」について「リレー」の形で進め、会場参加者との意見交換を通じて新しい日本事情教育の連携とその教科書のあり方を再考したい。